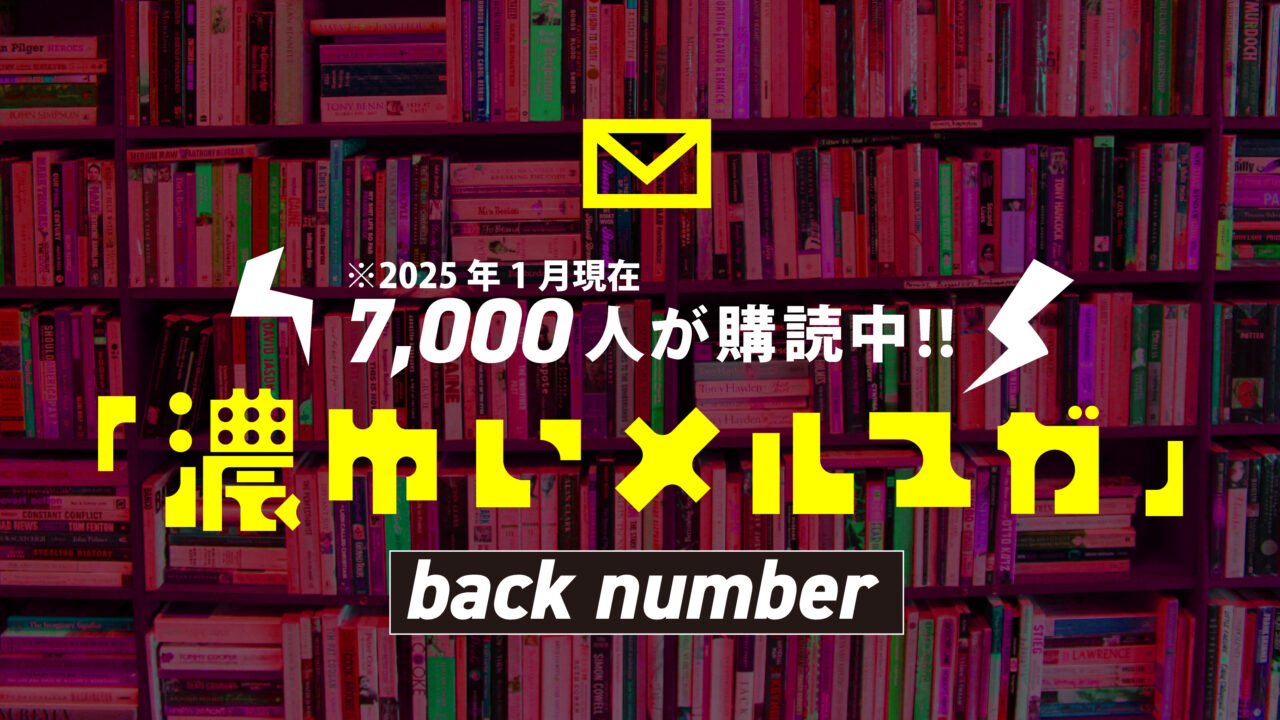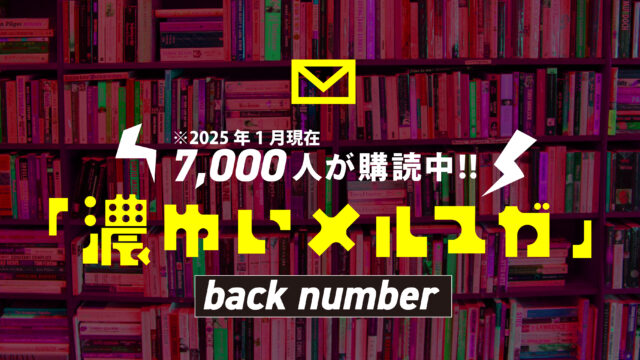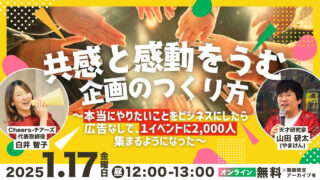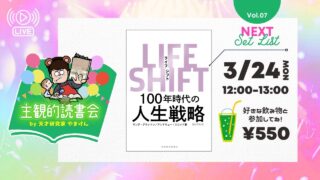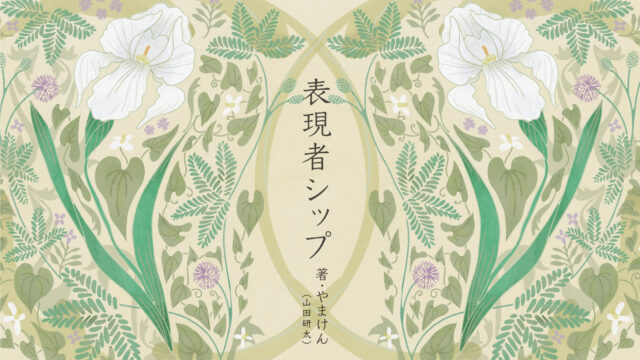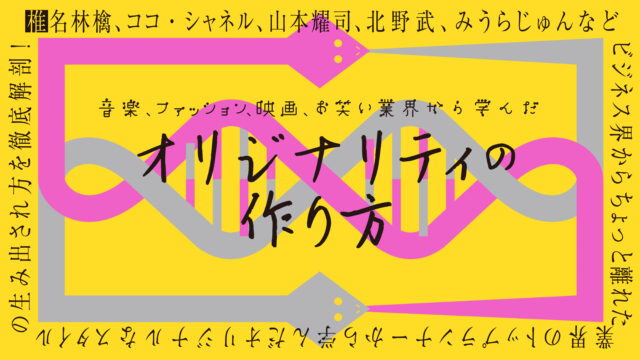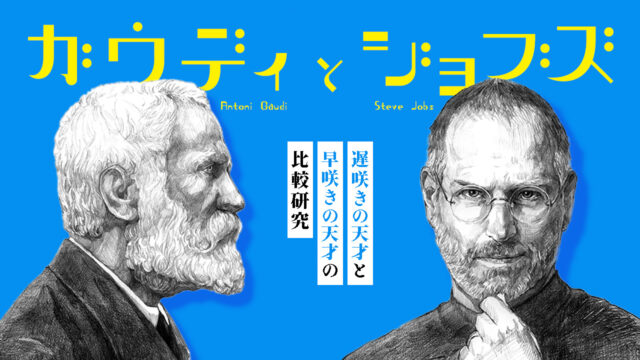この記事は、ぼくのメルマガのバックナンバーです。メルマガでは、「最新の天才研究についてや、ぼくがプロデュースを手がけるアート型ビジネスの最新事例など」について書いています。他にはない独特な長文芸にある種の中毒性があるとかないとか、噂されるそんな不普通のとはちょっと違った『変なメルマガ』です。メルマガはこちらから無料で登録できます。
通常はバックナンバーは公開してないですが、メルマガに登録しておくと本記事に転記されているような内容を全部で読むことができます。
【以下転記】2023/4/20のバックナンバー
こんにちは、やまけんです。
今回は、寂しさの解剖シリーズ第3弾です。前回の「大人になってから親友を作る勇気」、思ったより反響があって嬉しかったです。メルマガに初めて返信します、と言って感じたことをシェアしてくださる方も結構いて、うれしい気持ちでいっぱいなんですがそれらにすべて返信するだけの時間は取れてなくてすみません。返信の代わりに、今日も心を込めて必要な人に届くように全力で書きたいと思います。
・・・
と思って、本気を解放して今メルマガ書き終わったんですけど、昨日と今日で計7時間かかったんですけど、文字数をカウントしてみたら2万字ちょっとでした(笑)。こんなん誰が読むねん!!いや、これをみてるYOUだよ!
ってことで、1日で読んでもらえるとは思っていません。次のメルマガ送るまでちょっと間を開けるので、今回の主題である「寂しさ」や「豊かな満たされた人間関係」に興味がある人だけ、数日かけていいので読んでくださいませ。あと事業的に「チームづくりがしたい人」も後半は役に立つと思います。それ以外の人は、今回のメルマガは読まなくてよし!そのうち「幸せの土台」については扱うのが終わったら、ビジネスのことについても書くのでそれまでお待ちを!
一応興味がある内容があるかどうかを前もって確認できるように今回も「目次」を置いておきますね。ではどぞ!
- 寂しいからご飯に誘っていたわけではなかった!?
- 条件づけられた習慣とおしっこの件
- 無意識のうちに自ら「寂しさ」を作り出していた
- 何によって寂しさは解消されたのか?
- 飲み会の別れ際の寂しさは何が原因か
- 『ホンモノ経営塾』と『天プロ』ではサービスの作り方をこう変えたことで人間関係がより豊かなものになった
- 天プロを作ったあとでも孤独感があったポイント
- 短期で圧倒的な結果を出そうとするのをやめようと思ったきっかけと理由
- これまで自分が無意識的に追い求めていたものについて、1つ1つ本当にそれがいるのかを吟味していった結果…
- ホンモノ経営塾時代は、優秀な人材をチーム。それが今は
- 以前はチームメンバーに対して多少感じていた後ろめたさや罪悪感がなくなった
- サービスの設計やフィーの設定も大事にすることが変わった
- 結論:寂しさを解剖した結果
- いい人間関係のレベルを5段階にわけてみると
- 最後に『フロー体験 喜びの現象学』より引用
- 寂しさの解剖・完!感想求ム
寂しいからご飯に誘っていたわけではなかった!?
前々回のメルマガで昔は夕方になったら急に誰かを誘ってご飯にいきたくなってたけど、そういう気持ちが最近なくなったという話を書きました。この変化は、以前は寂しさがぼくの心の中にあったから、それが原動力となって人に会いたいと気持ちが発生していた。今は自分の心の中から寂しいという感覚がなくなった。寂しさという原動力であり原因がなくなったから、人に会って一緒に楽しくご飯を食べたいってあんまり感じなくなった。この寂しさシリーズを書き出した当初はそう思っていました。
でも、果たしてそうなのか?大枠では間違ってないけど、細かなところでは上の理解だと何かを見落としている感じがしたので、さらにいろんな視点から自分の日常的な行動習慣の変化(夕方疲れたときに誰かをご飯に誘いたいと思わなくなった)について考察してみると、あることに気づきました。
まず、仕事をいい感じで頑張れてかつ疲れた夕方どきに、誰かをご飯に誘いたくなるアレは、必ずしも寂しいという原因があることから生じている気持ちや行動ではないんじゃないかと思ったんですね。そうじゃなくて、単に昔ある時期に定着した習慣が残っちゃってるだけなんじゃないかと。
条件づけられた習慣とおしっこの件
人には、〜のときには〜するという習慣化された行動がいくつもありますよね。ぼくだったら去年までは疲れたら外でも家でもお酒を飲む。朝起きたら他の今日やるべきことを差し置いて、机に向かってノートを広げて思考タイムをとる。お酒を飲んだあとにラーメンが食べたくなる。みたいなやつです。ちょっと冒頭から話がそれるんですけど、みなさんはお風呂場でおしっこすることってありますよね?ぼくは何の疑いもなく、シャワー浴びてるときにおしっこしたいっていう気分になっら何のためらいも後ろめたさも感じることなくおしっこしてました。そっち方が自然で効率的だからねと思ってね、うん。最近までは。いや、そんなけしからんことするやつはなかなかいないでしょ、って思ったそこのあなた!ぼくも今ネットで「お風呂 おしっこ」って調べてみたら、一番上にヒットした総合南東北病院というサイトのこのページ(人に言えない困った症状ー「お風呂に入ったら排尿したくなります」)に、一説には男性の4割が排尿していると言われています、と書いてありました。ほらね?女性は知らないですけど、男性では結構いるみたいです。でね、ぼく夜1回おしっこに行きたくなって起きちゃうんですよ。起きて行ってまたすぐに寝れるから別に問題じゃないと思っていたんですが、これは睡眠の質が悪くなるから本当は朝まで起きない方がいいって誰かに教えてもらって。そんなことを考えてたときに、お風呂場でおしっこしてると夜起きておしっこに行きたくなりやすくなるっていう記事をたまたまネットで見つけまして。はじめはどう関係があるの?って思ったんですけど、お風呂でおしっこをするっていうのは体があたたかくなると尿意をもよおすって条件付けになっていると。だから夜布団に入って寝てて体があったまってきたら尿意をもよおす条件が満たされ、かつそういうときに普段は我慢せずに排尿してるから、眠ってても起きてトイレに行きたくなる。だから夜起きてトイレに行きたくなければ、お風呂場でしっこをするなかれ、みたいなことが書いてありまして。なるほど〜〜〜と唸ったわけです。この事実を知って以降、シャワー浴びてるときにおしっこしたくなっても、睡眠の質を高めて自分のパフォーマンスをあげるという、より優先順位の高い目標を達成するために、目の前の欲求を我慢するという(部分的には)不自然で非効率に思える(けど生活全体では夜起きないという意味で全体最適につながる)行動を学習したのであります。何の話やねん!って思ったかもしれませんが、これを書いてるぼくも思いました。でも、急に書きたくなったので、ここで自白して出してみることでものすごくスッキリしました。ああ、爽快感。お風呂場のおしっこは今後は別ですが、基本的にはそのときに湧いてきた衝動については、たとえそれが非常識であったとしても、著しく人様にご迷惑をおかけしないかぎり、ナチュラルに湧いてきたその衝動の通りに行動することをよしとしている人間なのであります。
さて脱線したので話を戻しますが、要するにですよ、ぼくは毎回寂しい気持ちから人をご飯に誘っていたわけではなく、「夕方になったから」ご飯に誘いたくなっていたという可能性に気づいたわけです。または「仕事をがんばっていい意味で疲れたからストレスを解消してくなって」ご飯に誘いたくなっていたわけです。ある時期から、多分28〜29歳ぐらいからだと思うんですが、今日は集中して仕事をよくがんばれたな〜って思ったら、その日の頑張り具合や気分に合わせて、今日は誰を誘ってどこの店に何を食べに行こうかなって考える習慣ができたんですね(ちなみに、仕事に全然集中できなかった日は、人に会いたいって思わないのでこの習慣は生じません)。こういう風に、あるときに何かを得たくてやったらそれが手に入ったという成功経験が繰り返されることによって作られた習慣のことを、心理学的な専門用語がもしかしたらあるのかもしれませんが、ぼくは「条件反射的残存習慣」という名前に命名しました。
でね、実は大事なポイントはここからです。寂しがり屋だから人を誘っていたって思ったら実は違った。単に条件反射的に以前からの習慣を無意識的に採用し続けてたから、そういう行動を取り続けてたんだっていう話だと、もしかしたら(夕方に飯に誘う習慣があった)1年前の時点ではすでに寂しさは十分に満たされていた(けど自分でその自覚がなかった)ってことになります。でも、実は話はそう簡単じゃなくて、夕方に誰かを誘ってご飯に行くという条件反射的残存習慣は、「結果として寂しさを生じさせる」ことになっていたわけなんですね。どういうことか?
無意識のうちに自ら「寂しさ」を作り出していた
ご飯に行くときは、その日の気分によって、いろんな人を誘っていました。よく誘う人もいますが、完全に固定化された人はいないんですね。いつも別の人とご飯に行くのは、「ストレスが溜まったら、刺激が強いものを欲する」っていう別の習慣からきていました。疲れたときに何を欲するのかは人によって違うと思いますが、休むとか安心感がある場所や人と過ごすことで癒されるっていう人が多いんじゃないかと思いますが、ぼくは疲れるとなぜか「楽しい」ことをしたくなってたんですね。これを読んでて「あー、私もそのタイプですっ」って人も意外といるんじゃないかな?ぼくの中で楽しさとは新しさを伴うもので、予測ができない複雑さや刺激があるものを欲してたんですね。そういうわけで、その日の気分に合わせて、誰と誰と誰を呼んで、あの店に行ったらどうなるんだろう?っていう複雑な組み合わせを楽しんでいたわけなんですね。
で、ここまではいいんですけど、実際に一緒にご飯に行ったら楽しいと。2次会も行ったりして終電ギリギリまで飲んでると、元々相性が良くて一緒にいて楽しい人だったらすごい話が盛り上がってるんでもっとしゃべってたいって思うじゃないですか。飲みがスタートしてから時間が経つにつれ、場があったまってチューニングされていくことで、普段だと話さないような恋話や深い話が出てきたりして。普段とは違うレベルでの話、またはその話をするときの感情を共有することで、普段どこでも誰にでもできるような表面的な話をしているときと比べて「深いつながり」を感じるわけですよね。普段は別々の場所に住み、それぞれの家族構成の中で、別々の目標や課題をもってそれぞれ過ごしている別の人間が、場があったまったその場ではひとつになるというか。それはやっぱりこの人のことが好きだなあって感情になるのかもしれないし、やっぱりこの人(たち)といると安心するとか、最近の中で一番楽しい時間だとか、この一体感が好きとか、この時間が終わって欲しくないとか、人によって言語化するときの言葉は違うけど、まあ何にしろ特別な感情を共有するわけですな。メンバーがよくて、いい会になったときの話ですよ。ただ、ぼくはいい場になるようなメンバーの組み合わせや店選びとか席配置、そしてその場での飲み会ファシリテーションが得意なので、意図すれば割とオーケストラの指揮者のようにその場にハーモニーを生み出すことができるんですよ。だから毎回、終わる頃にはまだ帰りたくないって気持ちになることが多い。
だがしかーし、どれだけいい場になったとしても、これから付き合おうとしている男女とかではない限り、その場での最終的な帰結は「物理的な分離」ってことになるわけですよ。家庭の門限なのか、終電なのか、眠気なのかが一体になったぼくたちを分かつ。そしてその後に必然的に生じやすい感情が「寂しさ」なわけですね。感深いつながり、一体感が生まれたからの寂しさ。感情的にひとつになって統合されたように思える状態から分離されたことによって、寂しいという感情が自然と湧いてくると。終電で帰りながらとか、それを逃してタクシーに乗って半分眠りながら、「あー最高に超楽しい時間だったな」とちょっと前までに味わっていた感覚や感情を振り返りながらも、「もっとこの時間が長く続けばいいのに」という気持ちがわいてくるわけです。
ということはですよ、もし仮にスタート地点である誰かをご飯に誘うっていう行動の原因が寂しさからきてなくても、ご飯が終わって解散するっていうゴール地点においては確実に寂しさが生じるという結果になっていたわけです。だから、週何回もご飯を食べに誘っていた頃の自分が寂しい気持ちが満たされてなかったかはわからないんですが、寂しい気持ちが頻繁に生じるような生活習慣になっていたというのはありそうです。
でもこれは、間のプロセスを吹っ飛ばすと、(例えそれが無意識的にでも)寂しさを自ら求めてに行ってたということも言えるかもしれません。ぼくは前回のメルマガに書いたようにぼくが多かれ少なかれ寂しさを感じていた期間が15年以上はあったので、ぼくの世界観は寂しさがあるのが当たり前という前提ができてしまっていたようです。実際には、本当の心のうちを話したいと思える相手、また実際にそれを受け止めてくれる相手がいないという物理的な人間関係の環境にいて孤独感を感じていた高校のときと最近とでは180度というか180000度ぐらい自分を取り巻く人間関係は豊かで満たされたものに変わっているのにです。なので、ぼくがすべきだったことは、現実認識が過去のある期間で止まったままになっている状態から認識を正しくアップデートすることです。今目の前にあることを見つけ、盲点になっていた現実から受け取るべきものを受け取り、今の自分が本当に求めているものは何か?を問い直すことでした。
何によって寂しさは解消されたのか?
といろいろとここまで書いてきたけど、結論はやっぱり、1年前より今の方がより一段人間関係的に満たされて、寂しさが解消されたなと思うんですね。盛り上がった飲み会の終盤で話が深くなっていったときに感じるようなつながっている感覚を、いつも当たり前のように感じるようになっていると。飲み会のときはお酒飲んでるのもあるので、つながっている感覚は「気分の高揚感」からもたらされるもの。それに比べて最近のつながっているという感覚は、誰かと対面で会って飲んでいるときじゃなくてもあるし、何だったら人とコミュニケーションしてないときでもあるので、以前の特別な感情を伴う感じとは違うけどね。
さて、じゃあ何が寂しさの解消につながる要因になったのかというと、ぼくの自分考察による結論は、去年からちょっとずつ作り始めた「チームメンバー」の存在によってだというものです。ただ、チームを作るっていうことそれ自体によってつながりの感覚を得られたかというと、そうではないんですね。ホンモノ経営塾をやっていた6〜7年前もチームを作っていたけど、そのときとはチームの作り方もチームメンバーとの協働からもたらされる感情や価値も大きく違うからです。これは今回言語化してみるまで気づかなかったことですが、やっと言語化できるレベルまでなってきたので、チームの作り方のついての具体的な違いについてもシェアしてみようかと思います。
飲み会の別れ際の寂しさは何が原因か
寂しさとは何か。つながりとは何か。一般的にはわからないけど、ぼく個人にとってこの2つが根本的にどこからきているのかを考えるにあたって、「飲み会がおわったときに感じる寂しさはナチュラルな感情なのでそれ自体は健全だとしても、何がさみしさをもたらしている原因なのか」というのを一歩掘り下げて考えてみたんですね。そしたらわかったのは、上に書いた文章の中で、この部分
>普段は別々の場所に住み、それぞれの家族構成の中で、別々の目標や課題をもってそれぞれ過ごしている別の人間が、場があったまったその場ではひとつになるというか。
からきているなと。
ここに書いてあることの中で、つながりに関しては、共有できるている部分の「重なりの面積の多さ」が大事なんじゃなかろうかと。実際問題は、家族になるとか一緒の場所に住むっていうのはないけど、同じ目標を共有するっていう感じだったらありえるなーと。だから、別の場所に住みながらオンラインベースで協働してて、リアルではたまに集まる感じだったとしても、「同じ目標」を共有してそこにそれぞれが主体的意欲的に向かえていたとしたら、飲み会で解散するときに感じる寂しさの度合いや質はまた違ったものになるんじゃないかと思ったんですね。ちなみに最近マズローの次に研究し始めたフロー理論では、フロー(深い没入感からくる楽しさ)を感じられるいい人間関係を築くためには、それが夫婦でも友人でも共通の目標を持つことが欠かせないと書かれてあり、なるほどなと思った次第です。
『ホンモノ経営塾』と『天プロ』ではサービスの作り方をこう変えたことで人間関係がより豊かなものになった
考えてみると、ぼくは『天プロ』というプログラム兼コミュニティを2020年7月に作ってから、ここではかなり豊かな人間関係をたくさん作ることができていたんですよね。1年前でも十分に。
なぜぼくからすると豊かな関係性だと言えるのかというと、ぼくが日々考えていることや興味を持っていること、またはいろんな研究をしている中で発見してシェアしたいことを、待ち望んだり喜んで受け取ってくれる人が天プロの中で一定数確実にいるからです。これはホンモノ経営塾のときはできなかったことです。あのときは、マーケティングという顧客を中心にした考え方で集客からサービスまで作っていっていたので、例えばプログラムの中でぼくが話すことは、求められていること、必要性的に自分が教えるべきことだったんですね。だから例え、ぼく個人としては伝える内容に対しては当たり前すぎて飽きてたとしても「仕事だから」という理由で、毎回同じことを違う期で伝えていた。そして同じことを毎回講義で話したり、同じような課題を解決するのに飽きてきた頃に、実際の運営を人に委任して引き継いだわけです。
それに対して「天プロ」は真逆の作り方をしました。お客さんではなく「ぼく自身が本当にやりたいこと」を中心にサービスを作り込みました。そっちの方が、飽きずに長いこと続けられる。そういう意味では、ぼく自身がそのときにやりたいことをやり、それを伝えることが良しとされるサービスにした方が、長くいいことを続けることができ、結果としてお客さんのためにもなると考えたんですね。
そんなわけで、自分が本当に大事にしていることや、今この瞬間に旬で伝えたいことを、「こんなこと求められてないかな」「これ言っても難しすぎて意味不明かな」と思ってアウトプットするのを躊躇する、やめるっていうことがなくなったんですね。これは経験したことがある人はものすごく共感してもらえると思うんですが、相手のニーズに関係なく自分が本当に伝えたいことを伝え、大事にしたいことを大事だと声高に言い、やりたいことを遠慮や我慢せずにやれる。そういう場があることはとてつもなく幸せなことだし、そういう自分起点での動機に混じりっ気がないけど多くの人にとっては必要性もないかもしれないものを、喜んで受け取ってくれ、次またそれらが提供されることを楽しみにしてくれる人がいることはほんとにほんとにありがたいことです。そういう意味で、twitterやFacebookはそういう場ではないけど、このメルマガは数年かけてそういう場にできたし(いつも読んでくれたり返信をくれたり他の人にメルマガを紹介してくださる読者のみなさんに感謝!)、天プロではさらに濃い話も共有できる喜びを感じられているので、天プロでできている人間関係はぼくにとっては宝物のように貴重で豊かなものになったと言えるわけです。
天プロを作ったあとでも孤独感があったポイント
ただ、そんな天プロメンバーでも共有できないことはありました。それはぼくの執着である「最高のプロダクトを作りたい」っていうことに紐づく、2030年ぐらいまでを目処に、天プロやアート型ビジネスをこんな状態に持っていきたい、天才研究を形にして本に出したいってことについての具体的な計画や実行についてです。大枠の方向性や全体の構想的な話だとめちゃくちゃ楽しみーって思って喜んで聞いてくれるんですが、そのために今月や今週具体的にどんなことをやるのかということになってくるとやっぱり共有するのは難しいんですよね。サグラダファミリアを建てるっていうビジョンとしての完成図にテンションがあがっても、じゃあここの石を22センチじゃなく18センチにした方がいいんじゃないかと考えていてみたいな話は、専門的すぎるし地味すぎて共有はできないわけですよね。そういう意味で、10年かけてかなり高い理想を実現しようとしていてそのビジョンに期待したりおもしろがってくれる仲間はいっぱいいるけど、それを実現する困難でありながら地味で地道なプロセスを自分ごととして共有できる同志はいなかったわけです。
ただ、ぼくの意識の中心はいつも、アート型ビジネスや天才本の完成にあります。いつなんどきもそのゴールに向かって時間を使っているわけですよね。なので、目に見えるわかりやすいアウトプットとして世に出すまでの、日々の具体的な活動について人と話し合ったり、日常的にコミュニケーションをとることができない点については、一抹の物足りなさがありました。「自分にとって一番大切な日々の活動を共有できない」という意味では、孤独感はあったのかもしれません。そういう自覚がなかったですけどね。でも、今の寂しさが解消されている状態がこんな感じっているのを知ると、前はそこは満たされていなかったのかもなーと気づいた感じです。
短期で圧倒的な結果を出そうとするのをやめようと思ったきっかけと理由
ホンモノ経営塾時代のチームの作り方と、今のチームの作り方は大きく違います。それは、シンプルにぼくが人生において求めるものが変わったからということに今回言語化していて気づきました。前は自分も自分のチームも、お客さんに対しても「短期的な結果」を求めていました。短期で圧倒的な結果を出したいっていうのは、高校生ぐらいからのぼくの基本的な価値観であり、それによってコンプレックスを解消し承認欲求(自分の自尊心)を満たしたかったんだろうと思います。短期で結果を出そうと思ったら、即戦力で活躍できる優秀な人をチームメンバーとして選ぶ必要があります。それ以外でも、承認欲求によって突き動かされているという意味では、場合によっては美男美女を彼氏彼女にして人から羨ましがられたいみたいな気持ちと同じように、「あんなすごい人、魅力的な人をチームメンバーにできているのってすごい」っていう風に人から見られたいっていう外ヅラを意識しての基準も内心は含まれていたのかもしれません。
ただ、短期的に圧倒的な結果を追求すると、ちょっとずついろんなところに無理が生じてきます。実力以上のことをやろうとするので、働く人の健康が多少犠牲になったり、短期的に結果を出せない人が自分に劣等感を感じて離脱したり、場合によっては離脱したことによる悲しみ→怒りの矛先がこっちに向いてアンチ的になるみたいなことも生じやすくなります。ぼくがそれらに気づいたのは、ホンモノ経営塾の事業をやめたときではなく、その後休んで復活してTwitterでブイブイいわして懲りずにイキってた後のことです。そのときは、すごい勢いでいろんな事業に着手して結果を出したりしていき、人はそれに注目するけど、体調を崩してチームから離脱していく人がちょこちょこ出るという状態でした。当初は、結果を出していくためには離脱する人がいるのは健全なことだし仕方がないことで、起業家はみなそういう経験をするものだと思っていたんですが、あるときふと立ち止まって考えてみたんですね。ぼくが本当に人生でやりたいことっていうのはこういうことなのか?って。何の疑いを持つこともなく、いろんな分野で他の人が出せないような結果を出すことを目標にしてきたけど、それは体調を崩して離脱していく人たちの犠牲の上に成り立ってるんじゃないかと。それを良しとするならいいけど、本当に自分はその犠牲を良しとしてこれからも進んでいきたいのか?と。
猛烈に結果だけを追ってアドレナリベースで日々の刺激的な挑戦や出会いに興奮し楽しんでいた状態から、立ち止まって1〜2ヶ月内省をした結果、いやそうじゃないよな、って気づいたんですね。ぼくが人生で本当に求めていることは、Twitterのフォロワーとかほとんどがあったことがない不特定多数の人に認知されてすごいと言って話題にされることではなく、自分が日々一番多くの時間をともにしている身近な人間、チームメンバーたちが健康で幸せであり続け、かつ心許せるそういう人たちと深い信頼関係を築いて長い間いろんな挑戦をしていくことだと気づいたんですね。それに気づいてから、高校1年生以来初めて、もっとも大事にする優先順位が変わったんですね。
高校1年(2001年)〜2019年夏頃まで
短期で圧倒的な結果を出す>人間関係
↓
2019年の夏頃以降
短期で圧倒的な結果を出す<深い信頼関係を長く続けていく
じゃあ、ビジネスとかそれ以外の分野で結果を出すっていうことはどう扱ったらいいの?って話になるわけだけど、それは「一緒に働く人が健康的に幸せでいられるという条件をまず満たす範囲で」事業を伸ばしいていく形に変えれば、自分が実現したい高い理想と、理想とする人間関係を両立できる。ここに気づいてから、手をつける事業を減らし、事業を成長させるスピードをかなりゆるめて長期の時間軸に変え、時間の使い方もSNSを伸ばすためにコメント返しとかに使っていた時間を減らして、たとえSNSの伸びが鈍化したとしても遠くて顔が見えないフォロワーさんに時間を使うより、まず身近な人にたっぷりと時間を使う形に変えていきました。
これまで自分が無意識的に追い求めていたものについて、1つ1つ本当にそれがいるのかを吟味していった結果…
短期で圧倒的な圧倒的な結果を出したいと思っていたのはなんでだったのか?っていうのも時間をかけて内省してみた結果、「多くの人からすごいと思って注目されたい」「自分よりすごい人たちに一目置かれる存在になりたい」「単純に、短期で何かを攻略していくプロセスが刺激的で興奮できて楽しい」に加えて、今回書いた条件反射的残存習慣のひとつで、無意識的に過去身につけたパターンをやろうとしていたからだということがわかりました。じゃあ、これらの動機について1つ1つさらに深掘りしていったときに
■多くの人からすごいと思って注目されたいは大事か?
→注目されることは嬉しいけど、身近な人が自分と一緒に働くことでさらに幸せにのびのびしていってるのをみれる方が嬉しいし、逆に遠くの大勢から注目されても身近な人が体調不良やその他理由で離脱していくと自分が本質的に関わる人が幸せになる取り組みができていないと感じて自尊心も下がるので、距離感が遠い不特定多数の人からすごいと思われるは結果としてあったらあったで嬉しいけど、それを求めにいく優先順位は今よりもっと低くても大丈夫そう
■自分よりすごい人たちに一目置かれる存在になりたい大事か?
→これも上と似てるけど、すごい人たちといるといろんな学びはあるけど、やっぱり身近な人たちといる方が安心できるし幸せも感じられる。なのでどっちの人間関係をより重視して時間を使った方が自分の幸福度があがるかを考えたときに、身近な人に時間を使った方が、ぼくが人生で求めている感情を得られることにつながりそう。よって、自分よりもすごい人たちに一目置かれる存在になるために自分もすごい結果を出そうするのをやめ、自分から積極的にご飯に誘ったりするのをやめ、声をかけてもらったら参加するというスタイルに変更。また、そういう結果が出している人たちに一目置かれるために、スタートアップの起業家たちがよくやるみたいに自分が将来こういう感じになりますっていう風に、自分の将来価値をアピールしたくなる習慣も矯正し、心許せる身近な人たちといるときのように自然体でいるスタイルに変更。それによって、すごい人たちが集まる会食に行ったときに、そこに集まる人たちの中で自分に興味関心を持つ人の率はぐんと下がったけど、自然体の自分でいたときに興味を持っている人とは背伸びせずに付き合っていけるので、それによって自分が今後もつきあっていきたいと思う人と無理して付き合わなくていい人が明らかになっていった。「成長したいんだったら、自分が居心地の悪さを感じるような目上の人たちに囲まれる環境に身を置いた方がいい」っていう話はよくあってそれはそれでぼくも同意するところはあるけど、今の自分は自分の頭で考えてやるべきことを積み重ねていくことでも成長できるし、それでも足りない思ったときだけピンポイントで学べる人たちと関わらせてもらって何かを教わるのがいいかと思った。第一人生で一番求めているものは結果よりも豊かな人間関係だってことが、「自分が人生で本当に求めていることは何なのか?」を考えたときにハッキリしたので、すごい人と関わる頻度が減ったことで自分の成長スピードが下がったとしてもぼくの人生の価値観において大きな問題ではない。大事にしたいことが大事にできてないことの方が問題だということを自覚できた
■単純に、短期で何かを攻略していくプロセスが刺激的で興奮できて楽しい
→これについては正直飽きてきていた。例えばTwitterを攻略したから、次はインスタを攻略するか、youtubeを攻略するかってなったときに、テンションが上がる自分とテンションがあがらない自分がいる。なぜなら何かを短期で攻略するっていうゲームは刺激的だから好きだけど、SNSでフォロワーを伸ばすっていうことについては、それを人生の中心目標に置くほどの価値は感じてない。だからどうなるかっていうと攻略しようしたときに思ったより手こずったら、これは割に合わないと思って早期撤退するし、攻略できたらできたでそのあとは飽きちゃってやめる。そうやってまた次に攻略できそうなゲームを探してってなるけど、攻略しちゃった後は(さっき書いたようにその対象自体には本質的には価値を見出してないことからくる)虚しさが残るし、エネルギーを短期集中でも大量に投下する活動が結果として全然積み上がっていかないっていうのはどうなんだろうと考えたときに、それはもう十分やったらいいやって思えてきた。なので、今度はこれまで一度も取り組んだことがない、どれだけ時間がかかってもいいから自分が本質的に価値を見出していて意味があると感じていることに対して長期で腰を据えて取り組むってことをやる方が自分の人生にとってよさそうだと思った。ただ、この短期で何かを攻略すること自体に薄々飽きがきていることに気づきながらも結局はやめられずにまた次のゲームを探すっていう風になってたのは、上で書いた2つの動機を満たす手段になっていたから。なので、多くの人から注目や尊敬されたいとか、尊敬するすごい人たちの仲間に入れてほしいっていう欲求を満たそうとすることが、自分のこれからの人生を豊かにすることにつながないと強く自覚して、手放すことができなければ、短期で圧倒的な結果を出すゲームからも降りることができなかった。そして、このパターンを2001年から2019年まで18年も繰り返していたので、短期で突き抜けた結果を出そうとする思考や行動を手放そうと思っても、なかなか簡単にはそういかなかった。例えば、毎日朝起きたらSNSをチェックして、昨日から何人フォロワーが増えてるかをチェックするのが日課って感じで、数字を意識するのが中心の生活が汲み上げられていたから。なので、過去の自分の思考や行動をアンインストールして、これからの自分が求めるものに合った新しい意識や時間の使い方、習慣に置き換えられるまでに1年ぐらいはかかったんじゃないかと思う。その間に何度も自分自身による心理的抵抗にあったし、数字が気にならなくなったかと思ったらすごい活躍している友人を見て心がざわついて羨ましくなってまた結果を出すパターンに戻したくなるみたいな揺り戻しに何回もあった。長年の習慣を手放して置き換えるのはすっごく難しいことを再認識した。
ここで書いてたのが、2019年の7月から2020年の6月ぐらいまでの1年間で、ぼくの体の中にある短期結果思考の血を抜き新しい血に入れ替え、新陳代謝が十分に行われて本当の意味で「新しい自分」に生まれ変わるまでの話。翌月の2020年7月に天プロをスタートし、そこから1年半後の2022年2月ぐらいから、思ってもなかったけど、ホンモノ経営塾のとき以来再びがっつりチームを作ってやっていく流れに自然となっていった。そこから1年ちょっとがたったナウである。
ホンモノ経営塾時代は、優秀な人材をチーム。それが今は
チームの作り方についてホンモノ経営塾のときの何が変わったのかというと、上にすでに書いたように前は短期で結果を出すために「優秀な人材を獲得」しようとしていたわけだけど今はその視点ではない。10年とか場合によっては20年とかっていう時間をかけて、本当にやりたい価値ある目標を実現していきたいってことなので、この長期目標にあったチームメンバーの選び方に変わりました。
まず目標が長期なので、チームメンバーに迎え入れる人の基準も「長く一緒に働けそうな人かどうか」をまず第一に重視するようになりました。それは本人が信頼関係を大事にできる人であることだったり、ぼく(や他のチームメンバー)との人間的な相性だったり、そもそも本人が一人でやることよりもチームで働くことの方が好きで自分を活かせるタイプだという明確な自覚があることなどが含まれます。前までは「本当は自分も自分で事業を持って拡大することをやってみたい」って思っているような人でも、その人の有能でその人が入ってくれた事業をかなり伸ばせそうだと思ったらその人のことをある種”口説いて”組織に加わってもらっていました。でも、今は口説くのに近いことは絶対にしない。どれだけその人が入ってくれたら短期的に助かったとしても、自分でやりたいと思っている人はいずれ自分でやる。で、現段階ではそういう風に短期だけ活躍する人を受け入れる器はないので、長期の目標を一緒に長い時間かけて実現していきたいと純粋に思ってくれる人だけをチームメンバーとして迎えるようになりました。
また、長期で目標を実現していく場合に大事になっていくことは、プロセスに自然発生的な楽しさがあり、プロセス自体によって報われるってこと。短期で結果を出す感じだったら、その都度達成感を感じられるけど、長期志向のチームだと、足元でやることは地味で地道なことが多い。地味だからこそ他の人、企業なら面倒臭くて途中でやめちゃうようなことを、長い時間かけて積み上げていくから、他にはできないユニークなことが形になる。そうなると、仕事の成果によってではなく一緒に働く人との日々のコミュニケーションによって満たされるに組み立てた方がいい。ということで、求める成果のために手段としてチームを作るというのはやっぱりあったとしても、限りなく目的的にチームを作るということを今は大事にしています。目的的にっていうのは簡単にいうと、「気の合う仲間と一緒にやりたいことができたらそれ自体が楽しいよね」ってこと。だから、「基本的な価値観を共有できる人間的に相性がいい人」であることがチームメンバーの条件のひとつになっています。自分で自分のことを満たす力があるっていうのもその一つに。だって自分で自分を満たせる人の方が、いつでも安定して気持ちいコミュニケーションが取れるから。だから今は能力がピカイチに高くても、コミュニケーションがなんかスムーズにいかないとか雰囲気的に毛色がちょっと違うみたいな人はチームにいれないようにしています。そういう意味で共通の体験をしているかどうかも、価値観の一致って意味ですごく大事なので、今は天プロメンバーの中からしかチームメンバーを採用していません。事業の拡大スピードをあげたいってなったら、お客さん以外からの採用もした方がいいってなるしホンモノ経営塾のときは基本そうしてたけど、少なくとも今の段階では事業の拡大スピードを追うよりも、人間的に相性がいい人だけ入れるっていう基準を高く保っていた方が、プロセスを楽めるから長期でもいけるっていう方向性にとっていいと思っています。
以前はチームメンバーに対して多少感じていた後ろめたさや罪悪感がなくなった
また、コミュニケーションの取り方や、事業の作り方、サービスの設計の仕方も以前とは違っています。以前は、短期で結果を目指すので本人の成長スピードよりも早く大きな責任を担わないといけないこともあったし、本人が理想とするライフスタイルと現状の働き方にギャップがあってもなかなか修正できなかった。成長スピードとビジネスモデル的にね。で、本当は本人はもうちょっと働く時間が少なくて家族とゆっくりできた方がいいんだろうなーとか、本当は本人は自分で事業をやれるならやりたいんだろうなーとか、本人が自分の仕事たちのチームから外れて一人で仕事をしていったらもっと稼げるようになるから申し訳ないなーみたいなところに対して、若干の後ろめたさや罪悪感みたいなものもあったのかもしれないと最近振り返ってみて思った。ホンモノ経営塾のときに一緒に働いていたメンバーの大半は、その仕事をするのが好きで価値を感じてくれてはいたけど、彼らの理想のライフスタイルの実現するっていうのはできなかった。短期ですごいスピードで成長するっていう目標を持ってたらそれは無理があるって話だけどね。
でも、今は口説かないっていったのと同じ論理で、ぼくが誘導したり啓蒙するわけじゃなく本人が本当に求めるものがチームで一緒に働くことで得られそうって人を入れてるので、ぼくがチームに入ってくれると助かるって言ったから他にやりたいこともあるけど今は一緒に働いてくれているような一面があるというより、「何の制限もないとしたら何をしたいのか?」っていうことを考えたときに出てくる要素が、ぼくとチームで一緒に働くことで一番実現しそうな人だけを厳選しているので、以前は少しあった後ろめたさや罪悪感がない。ぼくからしたくりものすごいありがたくて、相手も一緒に働けることがすごい楽しいって思えるのが基本。例えばフィーをもらえなくてもやりたいようなことが仕事になっているかというのはひとつの基準。まあときどきは、これでほんとに大丈夫かな?相手に負担かけすぎてないかなとか、やりたいことからズレてないかなって思うことがあるけど、そういうときはコミュニケーションをとってちゃんと聞くようにしています。なので、そこで勝手に想像するだけじゃなくちゃんと「答え合わせ」をすることで、不要な心配を抱く必要がないようにしているわけです。
サービスの設計やフィーの設定も大事にすることが変わった
じゃあこのことがどこにつながってくるかと言うと、フィーに設定にも関係してきていました。以前は、どこか自分に自信がまだ足りないところや、本人が他でやったらもっと稼げるからってことで、フィーを高めに設定していたんですね。フィーによって人が離れないようにしている部分もあったわけです。ただ、フィーを相対的にあげるということはその分損益分岐点があがり、やっている事業がコンサルティングという労働集約型のサービスなのでみんなが生み出さないといけない付加価値(粗利)や働く量も増えてしまうと。そうなると、フィーはあがるけど、それぞれが自分にとって理想のライフスタイルを実現するための時間的自由度は下がってしまうという矛盾があったわけですね。
今でも一緒に働いてくれるメンバーにできるだけ多くのフィーを払えるようになりたいっていう方向性は一緒なんですけど、いろんな困難があっても長期にわたって一緒にやっていけることが一番大事なんで、そことのバランスをしっかり見て組み立てるようになりました。ホンモノの経営が予期せぬ形で苦しくなったときに、「フィーをあげるのは簡単だけど下げるは難しい」って経営者がみんな一度は痛い目を見て学ぶ教訓をぼくも学んだので、今は予期せぬことが起きたとしても変わらず長く続けていける経営スタイルをより重視しようと思っています。短期的な成長率より、事業としての安定性ですね。かつ、フィーというのは本人が実現したいライフスタイルを実現するための一つの構成要素、お金という一つの手段なので、前みたいにフィーはあがるけどその分仕事量が増えて(それが本人が本当に望むことだったらいいけど)、自分が自由に使える余白の時間や家族との時間が減っちゃうと本末転倒になるんでね。なので、今はその人が働くのに使う時間全体に対して役務提供(として働かないといけない)の時間が半分ぐらいでも、ある程度欲しい収入が得られるようになるには、どういうビジネスモデル、どういうサービス形態にすればいいかを考えて設計していっています。だって、半分自由に使える時間があったらだいぶいいですよね?その時間もサービス提供に使いたい人はそうしたらいいし、何か気になる学びに使いたい人、旅行とかにいきたい人とかいろんな時間の使い方の理想はあるんでね。今すぐには無理だけど、どの観点から見ても全員にとっていい働き方やフィーの設定は何か?を何度も問いながら、数年かけてそれを実現していけたらなと思っています。多分3年あればかなり理想に近い状態に近づけるんじゃないかというのが現状の予測ですが。
結論:寂しさを解剖した結果
さてここまで、自分の思考を整理する意味でも人間関係まわりに関係する最近のことをとりあえず全部書いてみたんですが、ぼくの寂しさが1年前と比べるとものすごく少なくなった理由は、
- 人生の目的を共有できる同志(チームメンバー)ができたこと
- その人たちとのコミュニケーションをかなり増やしたこと
- そして、自分が関わることでチームメンバー自身やその先の家族が、関わらない場合に比べていい方向(理想的な生き方)に向かっているという実感を自分もメンバーも持てるようになることを目標にすることで
- チームメンバーとの日々の関わりを通して、マズローでいうところの下から3番目の愛と所属の欲求だけでなく4番目の承認の欲求も十分に満たせるようになった(身近な人に役に立てている実感はもっとも健全な自尊心の満たし方の一つだと思う)
- ことによって、「共有できる面積が少ない」人との時間を無意識的に求めてしまうことが減って、寂しさも感じにくい生活スタイルになった
ことによるんじゃないかというのが、「寂しさの解剖」におけるぼくの結論です。いつもつながっていると感じられる状態になったのは、同じような価値観を共有し、長きにわたって一緒に協働していけるメンバーがいて、かつそこに対して(いつか●●なことがあったら離れてしまうんじゃないかみたいな)不安がない状態をつくることで、背中を預けて、自分がこの人生で本当にやるべきことに集中できるようになっていってるからなんだと思います。だから今は、寂しいの代わりに「安心感と心強さ」がいつも自分の中にあるという感覚でしょうか。
いい人間関係のレベルを5段階にわけてみると
まあ、人生においてはいつ何があるかはわかりませんが、長い間抱えていた孤独感やそれに伴って生み出されたいろんな思考習慣、行動習慣をひとつひとつ見直し、条件反射的残存習慣をやめて置き換えていくことで、日々求める感情を感じながら過ごせるようになっていったっていうことなのかなと思います。
寂しさを解消する人間関係について整理すると
■仲間はずれにされることなく(たとえ表面的でも)普通にコミュニケーションを取れる人間関係がある
ーこれはぼくの場合は人生通してずっとあった
↓
■一緒にご飯に行こうと個別で誘える(誘いたいと思える)知人や友人がいる。ただこの段階では、すごく仲が良くても自分の非常識的な一面や自己中心的な一面を見せることには抵抗があることが多い
ーこれは高校までは(ほとんど)なかったけど大学以降はできた
↓
■自分が人生において本音で興味関心を持っていることをそのまま話そうと思える人、かつ相手がそれに興味を持ってくれたり受け入れて応援してくれる親友がいる。またダメな自分も見せられるし、困ったら相談できるし、相手もできることは力を貸してくれると思える人がいること
ー準じる人は大学時代にいたけど、メインでは前回書いた23歳にトビと再会して以降そういう人がどんどん増えていった
↓
■自分が日常であったことや気づきなどについて、話したいと思え、いつでも話したり連絡ができる相手が複数人いる(上の親友でもたまにしか会ったりコミュニケーションが取りづらいと日常的なコミュニケーションのニーズは満たされないので)
ーこれはホンモノ経営塾のとき以降は、人間関係に恵まれていたので大体手に入っていた
↓
■自分の人生の目的や目標、または今一番集中していることに関連するけど、すごいマニアックすぎたり難しくていくら親友でもずっとその話ばっかりはしていられないと思うようなことをいつでも共有できる人がいる
ーこれがこの1年ぐらいでチームができたことによって実現されたこと
という順番で、いい人間関係によって満たされる欲求を、より高度なレベルで満たしていくことがきるといいんじゃないかということです。
最後に『フロー体験 喜びの現象学』より引用
1年前まではチームを作ることを欲していなかったけど、実際ひょんなきっかけでチーム作りにトライしてみたら、事業的なメリットだけでなく、想像してたのの何倍も大きな充実度や豊かさを受けることができたということを考えると、「今特別それが欲しいと望んでなかったとしても」今の自分がもっている人間関係よりも1つ進んだ人間関係(上のやつでいうと1つ下の)を作ることを試みてみるっていうのは、結構いいことなのかもしれないと思いました。
前回のメルマガでも書いたように強調しておきたいのは、親密ないい人間関係は、大人になってからは特に待っていても自然できるものではないということです。なので、自分で意図して、そこに対しての優先順位を上げ、より人生を充実した楽しくて幸せなものにしてくれる人間関係を作りにいく努力をしないと、人間関係は今のままずっと続くことが多いよっていうことです。最後に、次回の第4回の主観的読書会(5/8の夜に開催予定)で取り扱う予定の『フロー体験 喜びの現象学』(チクセントミハイ著)から、同じような趣旨の記述を見つけたのでそれを引用して、紹介し今回のくそ長いメルマガを締めることにします。
交友は表出的な挑戦を続けない限り楽しいものとはならない。人がただ自分の外側向けの仮面を再確認するだけの「友人」、自分の夢や願望について何も問いかけない「友人」、自分に新しい生き方を強く奨めない「友人」に囲まれているとすれば、交友が与えてくれる朝鮮の機会を逃していることになる。真の友人とは時には一緒に馬鹿げたことができる人であり、いつも誠実ぶっていることを期待しない人である。それは自己実現という目標を共有する人であり、したがって経験の密度を高めようとする際に常に付随する危険を、すすんで分け合おうとする人である。
(中略)
人々は家庭と同様、友人関係も自然に生じるものと信じており、交友に失敗すると自分に同情するほかはないと考える。多くの関心を他者と分かち合い、多くの自由時間がある青年時代は、友人を作ることは自然発生的な過程のように感じられるだろう。しかし人生の後半では友情が偶然に生まれることはまれであり、人は仕事や過程を丹精せねばならないのと同じく、友人関係をたゆまず育てていかねばならない。
うん、そゆこと!
寂しさの解剖・完!感想求ム
ってことで、「幸せの土台を強化する」っていうテーマにおける「人間関係編」を、”寂しさの解剖”という3回シリーズにてお届けしてきましたが、これにて完です!!!
毎度のことここまで詰め込んで最後まで気を失わず読んでくれる読者の人がいるのかという、一抹よりもかなり大きな不安を抱えながらも、本当に必要な人は最後まで読んで受け取ってくれると信じて、全力で今書けるすべてをアウトプットしてみました。
ので、もしこの最後まで読んでくれた根気があるあなたは、今日も何か感じたことや気づきがあれば、ぜひ気軽に返信してもらえると嬉しいです。「おもしろかったです!」ぐらいの簡潔さでもいいんで。また、感動したからこれを読むといいと思った人に勧めてあげたいと思った人は、ぼくのメルマガの登録フォーム(https://mailchi.mp/honnmono.jp/magazine)と一緒に(←ここはちゃっかり)、今回のメルマガをご友人に転送してあげてくださいませ。
ということで長い間お付き合いいただき、ありがとうございましたー!次回は何書こうっかなー。幸せの土台を強化する、「仕事・自信編」とかについて書いてみようかな。もしこんなことについて書いて欲しいっていうリクエストとかあればなんでも送ってくださいませー。
では!
<全3シリーズ>
Vol.1「寂しさの解剖」
Vol.2「大人になってから親友をつくる勇気」
Vol.3「寂しさからつながりへと日常的な感覚が大きく変わったことについて書けることを全部書いてみた」←本記事

天才研究家やまけん(山田研太)が「アート型ビジネスの考え方と実践方法 」や「最新の天才研究事例」などについて不定期で書いているメルマガです。
他にはない独特な長文芸にある種の中毒性があるとかないとか、噂されるそんなメルマガで、7,000人以上の人が購読してくれています。
特に、アート型ビジネスについては実際のプロデュース事例を含めて、かなり具体的に解説していることも多いです。なので、SNSでの発信よりも、より濃ゆいやまけんの発信を見てみたいという方はぜひ登録してみてくださいね。