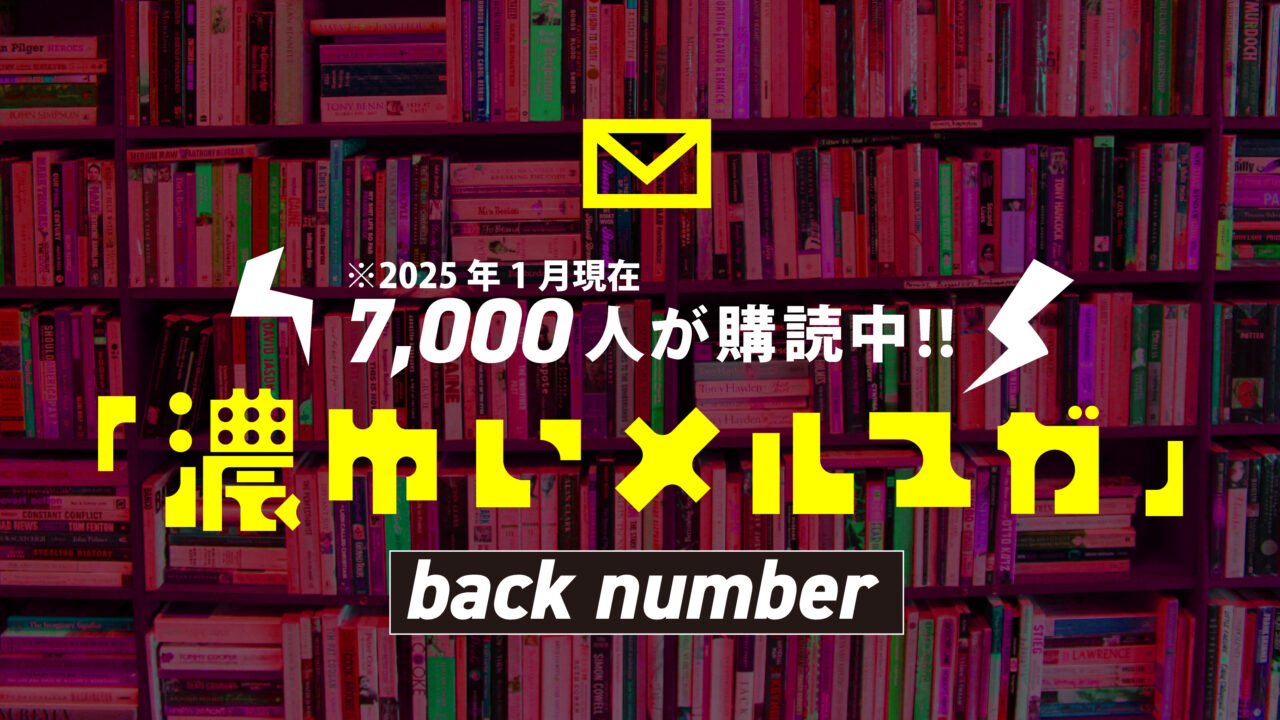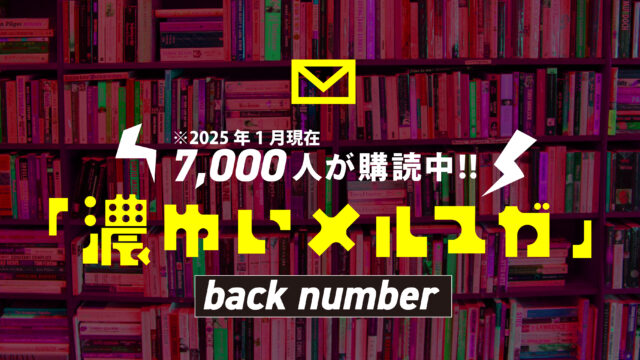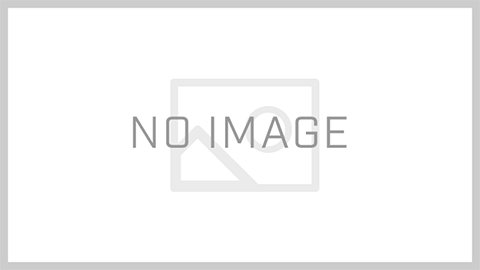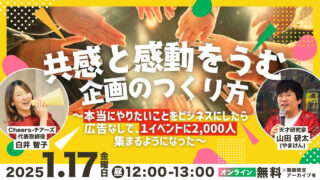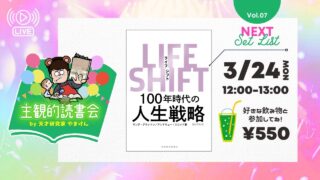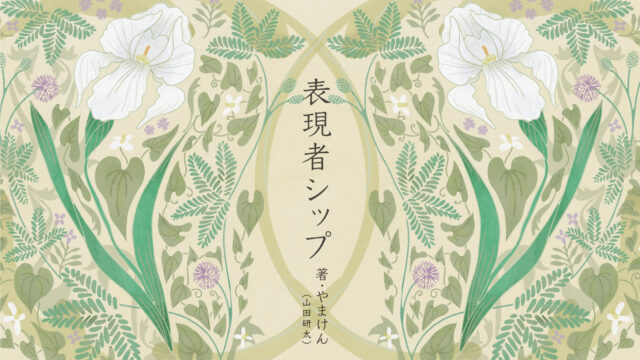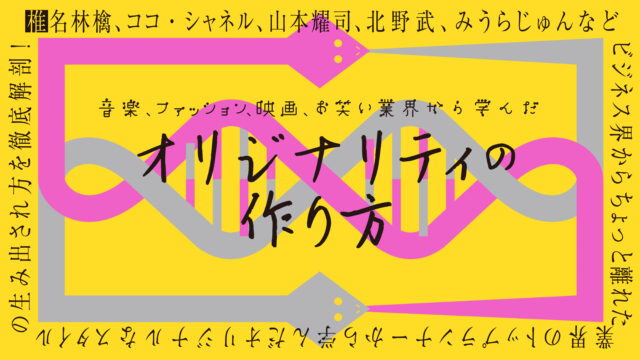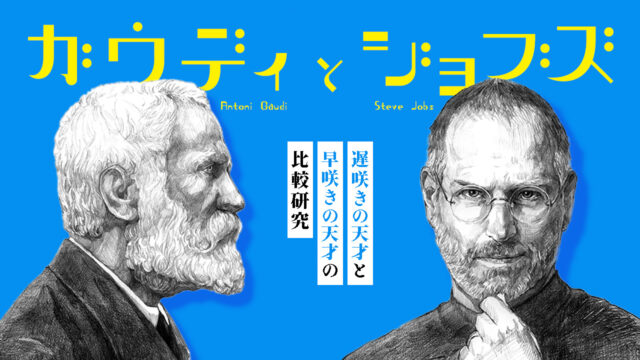この記事は、ぼくのメルマガのバックナンバーです。メルマガでは、「最新の天才研究についてや、ぼくがプロデュースを手がけるアート型ビジネスの最新事例など」について書いています。他にはない独特な長文芸にある種の中毒性があるとかないとか、噂されるそんな不普通のとはちょっと違った『変なメルマガ』です。メルマガはこちらから無料で登録できます。
通常はバックナンバーは公開してないですが、メルマガに登録しておくと本記事に転記されているような内容を全部無料で読むことができます。
【以下転記】2023/4/5のバックナンバー
こんにちは、やまけんです。
前回のメルマガ『借金を1億以上抱えたことで逆に見つけた、お金の不安から解放される方法』が大好評で、かなりの数の返信、感想をいただきました。ありがとうございます。あんなに長いメルマガを何回も何回も読んでくれた人がいて嬉しい!
ちなみに前回のメルマガの位置づけは、
>まず大前提として、『天プロ』というぼくが主催するプログラムにおいてのメインの目的は、本当にやりたいことで自分にしかできないことをビジネスにするという「アート型ビジネス」を完成させることです。そのプログラムにおいてまず最初に取り組むのが、この「幸せの土台の見直しと強化」なんですね。
ということで、「幸せの土台の見直しと強化」における”お金との付き合い方編”っていう感じだったんですね。で、今回からも引き続き、これまでそこまでメルマガでがっつりは書いてこなかった「幸せの土台」について掘り下げて書いてみようかと思っています。という流れで、今日は”人間関係編”です。
ぼくは人間関係で、ずっと悩んできた人です。悩みが重めなときと比較的軽めなときを合わせると、実は20年ぐらい悩んできたテーマなんじゃないかなーと思います。という背景があるので、今回、人間関係についてメルマガでアウトプットするために、過去から現在までの人間関係の変遷や、そのときと今とでは何が変わったのかを整理しようと思ったんですが、思ったより沼りました。ノートに書けば書くほど全然言語化できる気がしない・・・。そんな状態なのでおもしろいものになるかどうかはわからないんですが、自分の頭の中の整理も兼ねて書いてみようかなと思います。
寂しさがなくなってる…!?
そう感じたきっかけは、マズローの本を読んでいることです。本を読みながら、
- 自分の場合、どの欲求がどの程度満たされているのか?
- どんな手段によって満たしているのか?
- それぞれの欲求について、全然満たされてなかった状態から十分に満たせるようになった転換点はいつか?
- その転換点においては何が大事だったのか?
みたいなことを自分の現状に置き換えて内省してたんですね。
元々ぼくは、寂しがり屋さんです。天プロの初期の方のメンバーとかは、そのことを特によく知ってますが、寂しがり屋なので基本的に一人でご飯とか食べたくないタイプなんですね。誰かと食べたい。一人旅とか行きたいと思ったことは今まで一度もないし、実際に行ったこともほとんどないです。出張はありますが、その先ではお客さんと会ったりするんで厳密な意味での一人旅はほとんど経験したことがないんですね。お恥ずかしながら!
そんなぼくの昔からの習性は、その日の夕方前ぐらいになってくると、その日の夜の予定をどうするかなーってのを考え始めます。日によって気分は全然違うので、できる限り前もって予定は決めたくないタイプ。で、頑張ってよく働いたなーって日は、今日はよくがんばっていい気分だし疲れたらから「誰かと飲みに行きたいなー」ってなるんですね。そこから誰かを「今日の晩飯とか行けたりします?」とかって誘うわけです。2年ぐらい前とかだと「天プロメンバーで」「都内にいる人で」「その日の午後以降に声かけても来れる可能性がある人」の中から、声をかける。そうやって、1週間のうち半分以上は、飲みに行ってました。このときはぼくの中にはまだ、「寂しさ」があり、寂しさにという原動力によって動かされている行動が結構あったんじゃないかなと思います。
でね、話をマズロー本に戻しますが、マズローの本にこんなことが書いてありました。これは、ぼくが「執着とは何か?」をより具体的に定義しようとしていたときに、なんとなく考えてはいるけどはっきりとはわからない。うまく言語化できないっていう状態だった2ヶ月ぐらい前に大きな気づきを与えてくれたことでした。
ある欲求が満たされると何が起こるか?
マズロー本から、ぼくにとって大きな発見だった部分を引用しますね。『人間性の心理学』の第5章、「心理学理論における基本的欲求満足の役割」の中の小見出し〜一つの欲求を飽和させることの全般的結果〜より。ぼくみたいにこういう抽象的な文章が好きな人にとってはかなりわかりやすくおもしろい気がするけど、そうじゃない人にとっては難解で眠たくなるとも思うので、こういう難しい文章が苦手な人はこの引用部分は読み飛ばしてください。
※ちなみに太字の強調箇所はぼくが勝手に選んだ場所です。
どんな欲求でも、飽和させることによる最も基本的な結果は、その欲求が消えうせ新しいより高次の欲求が現れることである。その他の帰結は、この基礎的事実に付帯する現象である。そのような二次的帰結の例とは、次のようなものがある
一、これまでの古い満足や目標対象から独立し、それらを侮るようになり、それまでは見過ごしていたか欲しなかったまたはほんのたまにしか欲しなかった満足や目標対象を新しく求めるようになる。このように新しい満足が古い満足にとって代わることは。多くの二次的帰結を生む。興味にも変化が生じるのである。ある現象に初めて興味をひかれるようになり、古い現象はうんざりさせるものとなり嫌悪感を抱かせることさえある。これは人間の価値に変化が生じたと言ってよい。一般に(1) 満足されていない欲求の中で最も強力な欲求の満足要因を過大評価し過大評価し、(2)満足されていない欲求の中であまり強くない欲求の満足要因を過小評価し、(3)既に満足された欲求の満足要因(とこれらの欲求の強さ)を過小評価し価値を減じさえするなどの傾向が見られる。このような価値の移行の付帯現象として、未来・ユートピア・天国と地獄・良き生涯・個人の無意識の願望ー充足状態などについての哲学を、大体予測できる方向に再構成することがある。
つまり、我々は既に得ている恵みは当然のことと思ってしまう傾向がある。
(中略)
二、この価値の変化に伴って、認知能力も変化する。注意、知覚、学習、記憶、忘却、思考などこれらすべてが、有機体の新たな興味と価値によって大体予測できる方向に変化する。
三、(中略)有機体をより低次のより物質的でより利己的な欲求の束縛から解放させる最も簡単なテクニックは、その欲求を満足させることである(言うまでもなく他の方法もある)
要するにですよ、まず大事な点として、ある欲求が十二分に満たされると、その欲求はなくなるって書いてあるんですね。つまり、寂しさという欲求不満を埋めるために行動しているっていうことは、どれだけ人間関係の質と量があったとしても、現状では(何らかの理由で)まだ十分に満たされないてないですよーって証拠だし、逆にそれが十分に満たされた状態になると、たとえば一人でご飯を食べるのは寂しいから(または他の誰かと食べた方が楽しいから)誰かと一緒にご飯に行きたいって、まったく思わなくなるか、思う頻度がかなり下がるってことなんですね。
そして、さらに寂しさがあるということは、マズローでいうところの下から3番目の「所属と愛の欲求」、つまり人間関係に関連する欲求が十分に満たされてないってことであり、逆に人間関係が十分すぎるぐらい満たされて寂しさが解消されると、「所属と愛の欲求」が消えうせるが、その代わりに次の欲求、つまり4段階目にある「承認の欲求」がむくむくと現れてくるということなんですね。そして、ある欲求が消失し、ある欲求が現れるということは、その人の興味関心や好き嫌いも、それに合わせて大きく変わると。しかも、ある程度予測できるように変わると。
寂しがり屋は「タイプ」ではないのか
今まで夕方前になると、「今日は誰かとご飯に行きたい気分かな?」「じゃあ誰を誘おっかなー?」って考え、それを考えてる最中には、脳内でお酒を飲みながら楽しくご飯をしているシーンが再生され、それにともなうポジティブな感情が期待値として発生していたのが、そんなことを全然考えなくなるってことなんですね。その代わりに、「今日も1日成長できたかな?」「今日も自分が決めたことをやり切れたかな?もうちょっとやれそうだからがんばるかー」みたいに、頭の中に浮かんでくる問いやそれに伴う時間の使い方が変わってくるってことなんですね。
ってことはよ、なんとなく寂しがり屋ってのは、タイプの問題かと思ってたところもあったんですよね。うちのおとんもかなりの寂しがり屋やったから、遺伝的なところもあるんかなーと。もし、遺伝であれば、ずっと存在するものだから、寂しがり屋さんはずっと寂しがり屋としての満たしたい欲求があり、ずっと寂しがり屋的な「人と一緒に過ごす予定をいっぱい入れがち」という行動パターンであり続けるのかなと思ってたわけですよ。でも、違うのかと。そうじゃなくて、「十二分に」満たされたら、寂しがり屋のタイプでも寂しいと感じなくなるのか!って気がついたんですね。
ん?ちょっと待てよ。ってことは、寂しがり屋というのはそもそも”タイプ”ではなく、その人がどの程度人間関係で満たされているか、いう”状態”を現してるだけなんだと気づいたんですね(専門的なことはわからないけど、ぼくは現状そう解釈しましたって話ですので専門的には違うよーってことがあれば教えてくださいませ)。
そんなこと気づきに興奮していると、ふと思ったわけです。そういえば、最近めっきり会食が減ったな。前までの3分の1以下とかになったな。ということは・・・
(つづく)
1回で書くとすんごい長くなりそうなので、途中で区切ってみました。この気づきのあとにぼくの心の内側にある感情や感覚を探っていると、以前はあった「寂しいという感覚」がほとんどないような気がしたんですね。別の言葉でいうと、人ともっと深くつながりたいのにどっかでつながっていない感覚、みたいなのを時々感じることがなくなった(か極めて少なくなった)気がしているんですね。いつも、深くつながっているのが当たり前のようになっている感じ。
- これって本当に寂しがり屋を卒業したってことなの?
- もしそうだったとしたら、30年近く寂しがり屋だったのに、何がそうさせたのか?特に大きかった要因として考えられることは?
この辺について、(多分、予定では)次回書きたいと思います。
続きはこちらよりどうぞ↓
<全3シリーズ>
Vol.1「寂しさの解剖」←本記事
Vol.2「大人になってから親友をつくる勇気」
Vol.3「寂しさからつながりへと日常的な感覚が大きく変わったことについて書けることを全部書いてみた」

天才研究家やまけん(山田研太)が「アート型ビジネスの考え方と実践方法 」や「最新の天才研究事例」などについて不定期で書いているメルマガです。
他にはない独特な長文芸にある種の中毒性があるとかないとか、噂されるそんなメルマガで、7,000人以上の人が購読してくれています。
特に、アート型ビジネスについては実際のプロデュース事例を含めて、かなり具体的に解説していることも多いです。なので、SNSでの発信よりも、より濃ゆいやまけんの発信を見てみたいという方はぜひ登録してみてくださいね。