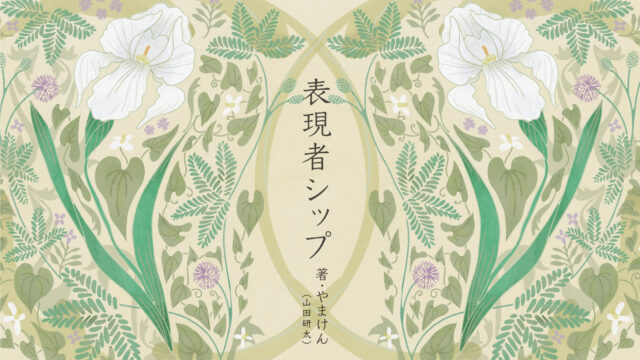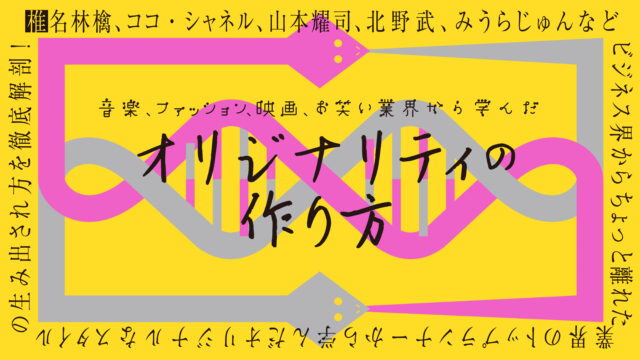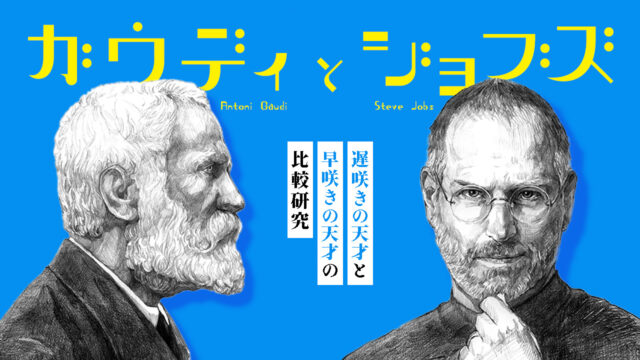この記事は、ぼくのメルマガのバックナンバーです。メルマガでは、「アート型ビジネスの考え方と実践方法 」や「最新の天才研究事例」などについて書いています。他にはない独特な長文芸にある種の中毒性があるとかないとか、噂されるそんな普通のとはちょっと違った『濃ゆいメルマガ』です。メルマガはこちらから無料で登録できます。
通常はバックナンバーは公開してないですが、メルマガに登録しておくと本記事に転記されているような内容を全部で読むことができます。
【以下転記】2020/7/10のバックナンバー
こんばんは、やまけんです。
前回書いた「箱根本箱」に行ってから何かのスイッチが入って、天才の研究が進んでいます。
下の本もその宿で見つけたものですが、「大して興味はないけど、天才ってついてるし一応読んでみるか…」ってぐらいの期待値で手にとってパラパラって目次読んだら、ピンとこなかったから本箱では全然読まずに帰りました。
でも、何かのヒントはあるかもしれないと思ってkindleで買って昨日から読みはじめたけど・・・
バチクソおもろいやないかああい!!!!
ぼくは勝新太郎のことを名前と中村玉緒さんが奥さんってことぐらいしか知らなかったから、どちらかといえば天才の研究の一環でじゃないと読まなかった本。でも、「はじめに」を読んだだけでめっちゃ引き込まれてしまった。
今半分ぐらい読んでるけど、ふつうに読み物としておもしろい。この著者が、本当に魂込めて書いたんだろうなってことがわかる。
”勝新太郎の本を書くのに1ミリの妥協も許されない”
そんな鬼気迫る感じが、文章からでも伝わってくる。で、ぼくが天才についての本を出すために、どうやって天才が生まれるのかを言語化できてから1週間ちょっとなので、ぼくの立てた天才についての仮説が勝新太郎に当てはまるかこの本を読んで検証してみようと思って読んだら、ばっちり当てはまってるぽかったので、その部分を引用しながら紹介しますね。
長いけど、今日のはだいぶおもしろいはずよ!では、どぞ!
この時期の勝の現場に台本はない。大まかな筋立てだけを用意して、あとは現場の即興の演出によって芝居は組み立てられていく。
「偶然生まれるものが完全なのだ」
それが勝の思想だった。勝にとってフィルムが原稿用紙なのだ。
(第1章の中の「演出風景の録音テープ」より)
その当時でも今でも、台本がない中で作られる映画やドラマなんてものはない。
ぼくの好きな映画『マジックアワー』で、主演の妻夫木聡が演じる主人公が、とあるアクシデントによってヤクザのボスから殺されそうになるが、なんとか難をのりきるために、一世一代の大芝居をうつってことで、台本なしで映画を撮るっていう喜劇な映画があるけど、もちろん台本なしの映画を撮るっていうこの映画には台本がきちんとある。当たり前ですよねw
でも、この本を読むと、勝さんがいかに”台本なしの即興”にこだわったのかが分かる。それにはもちろん、そうに至った原体験と、勝新太郎の気ままで飽きっぽい性格は関係するけど、それに巻き込まれるスタッフはたまったものじゃない。不安だし、巻き込まれ、振り回されて大変すぎる、っていうのが本書を見ていったらよく分かります。
僕は”天才の定義”を、「自分から見て真似できないことができて尊敬に値する存在」ってしてるけど、台本なしで映画をつくる様子は誰も真似できないし、真似したくないし、真似するべきでもない。
この規格外のあり方に、彼が天才と呼ばれた所以がある。
ただ、最初から天才として世の中に華々しく出ていったわけじゃない。同じ時期に映画でデビューをした、いわば同期的存在にあたる市川雷蔵は一気にスターの道をかけあがっていく。若手スターの有望株として、事務所から大々的に売り出されいた雷蔵とちがって、勝新太郎は、低予算でキワモノ・B級感が漂う映画にしか出演させてもらえなかった。
つまり伝説的なスターは、落ちこぼれからその道をスタートしたんです。だから、今回の題材としてぴったりだなと思って、細かめに引用してメルマガで扱うことにしました。はじめから天才でした、じゃあおもんないんでね。
で、ここからが、落ちこぼれだった、駆け出しの頃の勝新太郎について。彼がとった行動は・・・
雷蔵に追いつくために、勝は当時の大映トップスター・長谷川一夫に近づく。長谷川の付き人に手伝いをしながら常にその傍にいて、彼の芸を盗もうとしていた。そして、ことあるごとにその一挙手一投足に注目し、それを参考にしていた。
「芸事の修行は、毛穴でおぼえ、耳でぬすむもんなんだよ」
という父の教えもあり、勝にとって、芸はまずマネをすることから始まるという意味があった。
(第2章の中の「数合わせの主演作」より)
そう、ビジネスで、うまくいってる人をモデリングする、TTP=徹底的にパクる、と言われるように、勝さんも今一番うまくいってる人のマネをするところからスタートをきった。
当時の映画界は二枚目スターの全盛期。その頂点に君臨する長谷川一夫のマネをすることが。スターへの出発点だと考えていた。甘い声のセリフ回し、女性の心を溶かす流し目、微笑みをたたえた表情、白塗りのメイク・・・勝は自らを美しく飾り立て、若き日の長谷川のような二枚目像を受け継ごうとしていく。
(第2章の中の「数合わせの主演作」より)
ただ、その結果は・・・
勝の意気込みにもかかわらず、その主演映画は一本として当たらなかった。
見栄えの美しさを何よりも追求する長谷川の芝居は、勝本人のパーソナリティに似合わない芸風だった。だが、本人も会社も、まだそのことに気づいていない。二枚目スターの全盛の時代に、他の選択肢はなかった。
(第2章の中の「数合わせの主演作」より)
そう、まったくうまくハマらなかった。
「突き抜けたいけど、どうやったら突き抜けられるのかまだ全然見えてない」
現状でそう感じている人は、この本の第2章を読むとものすごく共感すると思う。どうしても一流のスターになりたいから、思いつく限りの努力はしてる。人一倍努力してるけど、結果どころか一向に芽が出てる感じもしない。
「自分には才能がないんじゃないか・・・」そう思えてくる。ちなみに去年末の12月から年始の1月にかけては、ぼくも似たような気持ちだった。周りをバケモノのようにビジネスが得意な”ビジネスの天才たち”に囲まれていて、彼らと自分を比較して落ちこんで自信をなくしていた。
じゃあ、そんなときにどうすれば、「天才へと覚醒」できるんだろうか?今なら分かるけど、そのときはまだ覚醒へのステップが全然見えていなかった。
そんな時に出会ったのが、「ヌーベルバーグ」だった。フランソワ・トリュフォー、ジャン=リュック・ゴダール、ルイ・マル・・・フランスの若手映画監督たちが、ドキュメンタリータッチの荒々しくも躍動感のある映画を武器に、従来の映画の常識に挑戦していったこのムーブメントは、世界中の若い映画人たちに衝撃を与えていた。勝と森田も、またしかり。
(第2章の中の「役者としての目覚め」より)
ここで、外的要因として、世界の映画界で起こっている一つの大きな流れのことが書かれている。
一方、勝はルイ・マルの『死刑台のエレベーター』に衝撃を受ける。
(中略)
『死刑台のエレベーター』は、背景音楽にありきたりの劇伴ではなくモダンジャズを使うというスタイリッシュさが高い評価を受けていた。音楽への強いこだわりを持つ勝もまた、こうした音楽の使い方に感心する。映画のために用意されていた音楽ではなく、全く別の世界から楽曲を引っ張り出してきて組み合わせる自由さに魅かれたのだ。勝は、はじめて「芝居」を離れて「映画」の楽しさを知る。
そして、この感激は、旧態依然とした大映時代劇への不満へと向けられていく。(第2章の中の「数合わせの主演作」より)
大きな変化は、多くの場合、自分の内的な動機だけで完結して起きるものではない。普段の自分にとっての常識を超えた”新しい何か”に触れたときに、急速に問題意識が形成されることがある。
今回の「ヌーベルバーグ」というムーブメントが、勝を自分の演技から、そもそもの”映画のあり方”に目を向けさせ、現状への不満を生み出したように。突き抜けたいという思いと、新しい思想との出会いが勝新太郎をこれまでの延長線上にはない行動へと導いていきます。
同じ年、雷蔵主演の『薄桜記』で勝は堀部安兵衛を演じている。雷蔵は全身をメッタ斬りにされる破滅的な美しさを見せているが、勝はその対局を行った。躍動感あふれる野性的な演技をする一方で、討ち入りと恋慕の情の間で悩み苦しむ弱さを見せている。それは雷蔵の世界に真っ向から挑戦しようとしているのであった。特に前半部では雷蔵を完全に凌駕し、実質的な主人公になっていた。
ー役者として勝ちゃなんは目覚めようとしている!
『次郎長富士』『薄桜記』の助監督をしながら、井上昭は勝の変化を感じ取っていた。(第2章の中の「数合わせの主演作」より)
”目覚めようとしてる”
この表現はまさに、覚醒への予兆だ。今までの、現状で成功している人のマネを徹底するというスタンスから一転、その逆をやろうと初めて試みた瞬間だった。
ただ、奇をてらって、逆をやって目立とうとしてたわけではないことが、ちょっと長いけど、下記の対談部分を読んでもらえると分かる。
雑誌『時代映画』ー九五九年十月号には、そんな役者として「目覚め」つつあった当時の勝が、その心境を余すことなく語った対談が載っている。その対談の相手は他の誰でもない。ライバル・市川雷蔵だった。勝は雷蔵に向かって、思いのたけをぶつけている。
<勝「僕は今まで、現在いる俳優さんのモデルを頭に入れていたんだ。で、あの人ならこうする、この人ならこうするとかを考えてやっていたんだ。最近そういうのをなるべく避けて、そのモデルを、役者ぢゃない、普通の人を頭にいれてやっているんだ。その方がいろいろなものを出来るえ。いろんなモデルを自分は持っているということになるから」
雷蔵「演技をどこから、引張り出すかということは、なかなか難かしい問題だね。しかし、人の真似をするのはよくないだろうな。だから人によっては、人の芝居は全然見ないという人もあるわね。その人の良いにつけ、悪いにつけ、そういうものが頭にあると、自分が芝居をしている時に自分の素直な演技が出来ないのでよくないという、一つの理論があるわね。やっぱり真似はよくないと思うね」
勝「最近ね、僕もその真似ということから離れたのは。僕はどっちかというと、直ぐ真似の出来ちゃうほうなんだ。しかし、最近はいろんな役をやって来て、人の真似だけではとても追っ付かないものがあるんだな。(中略)しようがないから、自分で考えてやる。すると、その方が良いんだな。そこで今までのモデルではいけないんだなと始めて気が付いたわけだ」>演技者として先行し、既に確信にいたっている雷蔵に対し、勝はようやく役者の何たるかに気づき、試行錯誤をしながら雷蔵に追いつこうとしていた。そして、自分がスターになるために習得した「長谷川一夫のマネ」は捨て去りたい過去と化していた。
(第2章の中の「役者としての目覚め」より)
上の対談の中で勝新太郎が言っている「しようがないから、自分で考えてやる」というのが、天才性を発揮するための条件だとぼくは思っています。
ただ、マネすることでうまくいってたらそれはそれでいいはずだし、自分なりの方法を確立しようとはならなかったはず。徹底的にマネをするというのをやりきってみたけど、まったく結果が出なかった。でも、スターになる願望というか、そこへの執着が消えることはない。
その結果として、マネすることをあきらめて、自分独自のスタイルを身につけていこうとする。
勝の中で、何かが吹っ切れようとしていた。
ある日、ふとつけたテレビ番組に勝は吸い込まれていく。舞台中継の番組で、そこでは十七代中村勘三郎が悪の限りをつくす坊主を演じていた。貧しい盲目の鍼医者が、金を盗み、女を犯し、人を殺しながら検校の位にまで上りつめ、やがて破滅していくという強烈な物語。それが『不知火検校』だった。
「これをやりたい!」
それは本能の叫びだった。
「この役なら、雷蔵には絶対に出来ない。オレにしか出来ない芝居が出来る!」(第2章の中の「この芝居は雷蔵には出来ない!」より)
自分独自の道を切り開く。
そのモードにスイッチしよとしはじめると、それにあった機会を見つけるアンテナが通常よりも敏感になります。勝さんにとって、この作品はそのアンテナにばっちり引っかかったので、本能的にこの作品に力をいれると決める。そして、この作品が、天才性を開放していくあり方をつくる第一歩になります。
井上昭は、今回の勝に、いつもと違う様子を見ていた。いつもなら現場でジョークを飛ばし、スタッフと和やかな雰囲気で撮影を進める。それが、今回はひたすら役作りに打ち込んでいた。たまに口を開くと、森一生監督に次々とアイディアを出していったという。
勝によるオリジナルのアイディアの最たるものが、ラストシーンだろう。当初の脚本では、悪事が露見した不知火検校が役人に捕まるところで映画は終わっていた。何かが足りない。そう思った勝は、スタッフルームの森田に持ちかける。
「捕り方に囲まれたところで、周りに集まった野次馬に石を投げつけられるッシーンにしよう」
勝の提案を受けて森田が燃える。(第2章の中の「この芝居は雷蔵には出来ない!」より)
才能関連の本を読んでいくと、必ず出てくる概念が「フロー体験」であり、スポーツでいうと「ゾーンに入った状態」です。
このモードに入ると、集中力が研ぎ澄まされ、創造性が爆発します。勝さんが普段の現場と違って、アイデアをどんどん出していったのは、まだそれが結果に繋がる前から、”いま進んでる方向は正しいよ”という脳が発するサインです。
石を投げつけられ、顔面を血まみれにしながら、捕り手に引きずりまわされていく不知火検校。これを手持ちで凄まじく揺れ動くカメラが追う。その荒々しさは、二人の理想としていたヌーベルバーグの映像さながらの躍動感と臨場感であった。
(中略)
このときの石は当然、作り物だ。が、勝が石をぶつけられるたびに、井上昭は戦慄を覚えた。勝は本物の石をぶつけらあれているのではないか。そう思わせてしまう痛々しいまでの迫力が、勝の演技にはあった。
ーーついに、ここまで来たか!
井上の目には、勝が上昇気流に乗っているように映っていた。
それは、なんとかして自分の現状を打破しようとする、勝の執念の結晶だった。(第2章の中の「この芝居は雷蔵には出来ない!」より)
その後、『座頭市物語』という運命の作品に出会い、完全に覚醒。「誰かのマネ」をはるかに超えて、「誰もマネすることの出来ない」日本映画界を代表するスター=天才へ君臨していく。
そこへの流れは、この本を読んでもらったら詳細が書いてあるので、興味ある方は見てもらったらと。
で、こっから最後のまとめを。本がものすごく良かったので、できるだけ引用を使って今日は書きたいと思ったんですが、「落ちこぼれ、伸び悩んで突き抜けられず悶々としていた状態から、覚醒をしはじめて、後々に天才としてぶっちぎって突き抜ける」までに、何が大事な要因だったのか?
ぼくの中では、”異質性がある天才は、落ちこぼれか変人か、のどちらかの出身”、と言っていますが、勝新太郎は、落ちこぼれの出身であることが分かります。
- はじめから突き抜けていたわけではない
- むしろ最初は全然パッとしなかった
- 常識的なやり方を学んで突き抜けようとしていた
からです。
で、ぼくの周りでも”落ちこぼれ出身”の天才のルーツ・ヒストリーを聞いていくと、同じような条件が揃った中で、天才として覚醒していくことが分かったんです。
【覚醒に至る条件】
1. どうしても「こうなりたい」という強い執着がある
2. 努力を重ねてもそこにたどり着かないと気づく
勝新太郎でいえば、真似していても突き抜けられないと気づいたわけです。なぜなら、
・マネするのが人よりもかなり得意な自分が
・一番真似すべき良い対象を選んで
・できる限りの努力を尽くして真似したけど
・まったくもって結果が出なかった
からです。
ここではじめて、”今のやり方ではダメだ”ってなる。
そのときに、どうするかって言うと
・裏ルートを探す
・独自の方法を構築する
のどちらかを選びます。
勝新太郎がそうだったように、必ずしもはじめから独創的にいこうと思っていたわけじゃない。他の先人や今うまくいってる人がやってるやり方では自分は勝てない。執着しているものを手に入れられない。
この落ちこぼれの現状を前にし、圧倒的な窮地を自覚したときに初めて、「それでも、得たい結果を手に入れるためには、どんな方法があり得るのか?」という”自分独自の情報探索レーダー”が起動します。
自分で考えることで、人がマネできない方法、マネしたくない方法を思いつきます。この正攻法でいくことをあきらめ、失敗してもいいから自分独自の路線でいくんだ!ってふっきれたときに、「天才は覚醒への一歩」を踏み出す。
だから、天才の天才性は、”窮鼠猫を噛む”的な、窮地が転じてオリジナリティある方法や存在になっていくことが多い。それがぼくが最近つきとめたひとつの結論です。
ちなみに、本当の意味であきらめるには、やりきることが必要です。努力が足りてない段階では、もうちょっと努力すればいけるんじゃないかって思ってるので、正攻法をあきらめられません。やりきったけど無理だってなったときに、「自分が向く道」を歩みはじめます。
なので、突き抜けて悩んでいて、ここまで読んだ方は、読む前に比べて自分がやるべきことがクリアになったはずです。
・今やっている方法をやりきるか
・今のアプローチをあきらめ自分の頭で考えはじめるか
そのどちらかです。
ぼくも、まったくおなじステップを経て、他のビジネスコンサルタントとは一線を画した「変なメルマガ」を5月からはじめるに至っています。画期的なアイデアを思いついた!というポジティブな形ではじまったんじゃなく、もっと突き抜けたいけどこの方法だと今までと変わらないと半年ぐらいもがき、
そこでこてつさんや坂田さんといった、普通のビジネスとはちょっと離れた考え方で突き抜けている人たちに、プロデューサーとして深く関わっていく中で、勝新太郎が「ヌーベルバーグ」のムーブメントから何かの着想を得たように、ぼくも独自の路線を歩む道をスタートしました。
ただ、「天才」についての話は序章も序章です。
ぼくは昨日この本を半分ぐらい読んだ時点で、次々に気になる疑問が出てきました。
・”変人出身の天才”はどのような道を歩むのか?
・孤独になる天才と、孤独にならない天才の差は何か?
・天才に振り回されて破綻するチームと、なんとか持ちこたえるチームの差は何か?
と思って調べると、ずっとずっと気になってたけどまだ研究をスタートできてなかった、スタジオジブリで宮崎駿さんを支えるプロデューサー(ぼくの概念でいうと「保護者」)である鈴木敏夫さんが最近出した本で『天才の思考』ってのがあるじゃないですか!!!
そんなわけでその本を並列して読み始めたり、(おもしろくても多動ですぐ飽きるので)南海キャンディーズの山ちゃんこと、山里亮太さんが書いた『天才はあきらめた』などを深夜に読んで、天才研究を進めていました。
「やっぱりな」って感じる大部分と、「そうなんだ」という一部の発見を両方脳内に収納しながら、着々と天才本への準備を進めています。
天才については、もっともっともーーーーっと書きたいことがあるので、本としてみなさんにお届けできる前に、このメルマガで書きていきますので、楽しみにしていてください。

天才研究家やまけん(山田研太)が「アート型ビジネスの考え方と実践方法 」や「最新の天才研究事例」などについて不定期で書いているメルマガです。
他にはない独特な長文芸にある種の中毒性があるとかないとか、噂されるそんなメルマガで、7,000人以上の人が購読してくれています。
特に、アート型ビジネスについては実際のプロデュース事例を含めて、かなり具体的に解説していることも多いです。なので、SNSでの発信よりも、より濃ゆいやまけんの発信を見てみたいという方はぜひ登録してみてくださいね。
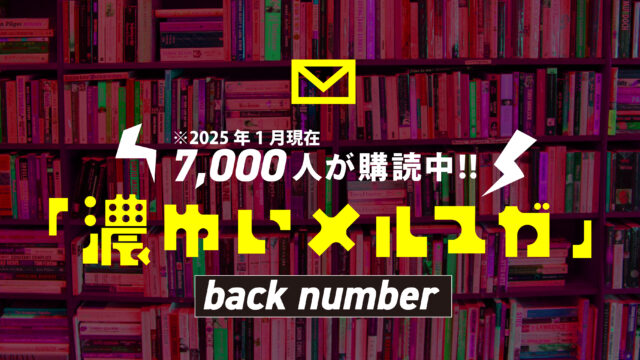
-現代ビジネス-講談社(3-5)-320x180.png)