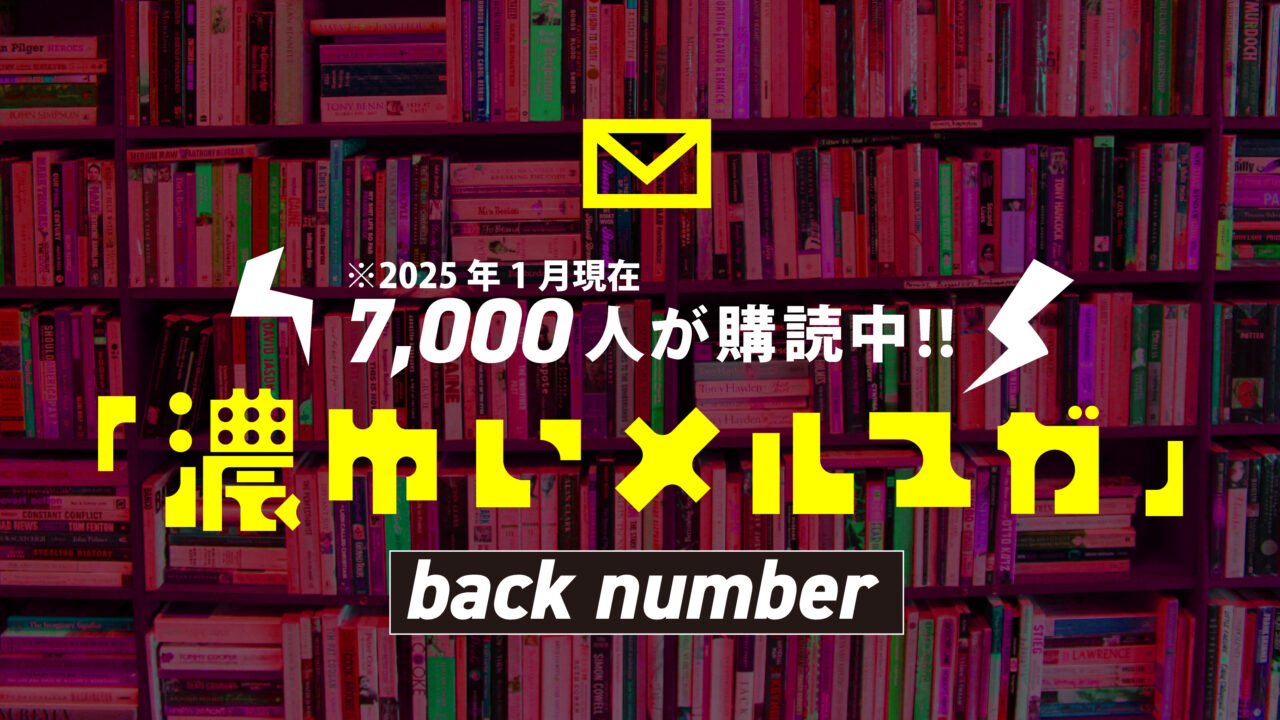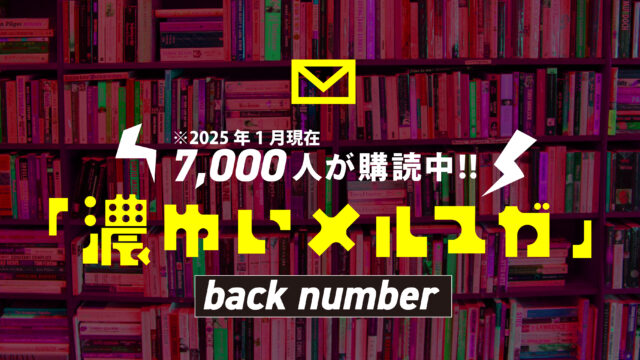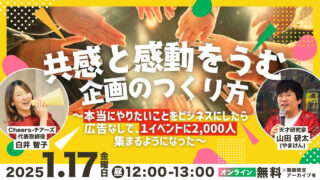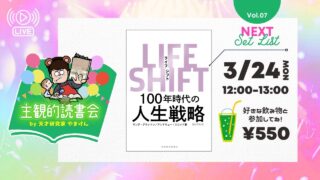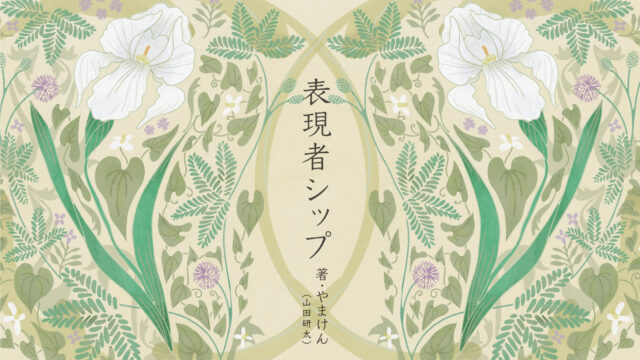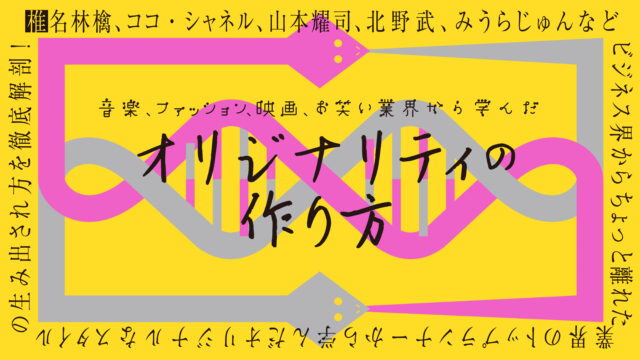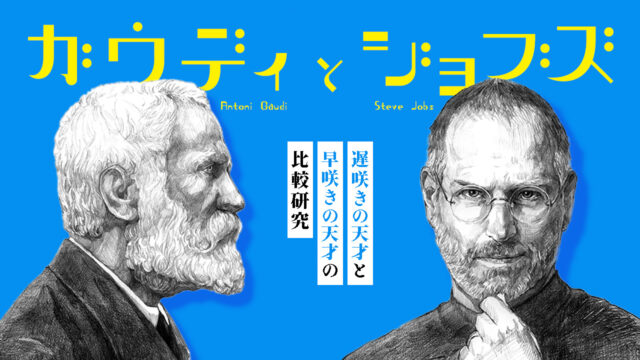この記事は、ぼくのメルマガのバックナンバーです。メルマガでは、「最新の天才研究についてや、ぼくがプロデュースを手がけるアート型ビジネスの最新事例など」について書いています。他にはない独特な長文芸にある種の中毒性があるとかないとか、噂されるそんな不普通のとはちょっと違った『変なメルマガ』です。メルマガはこちらから無料で登録できます。
通常はバックナンバーは公開してないですが、メルマガに登録しておくと本記事に転記されているような内容を全部で読むことができます。
【以下転記】2023/4/8のバックナンバー
こんにちは、やまけんです。
前回の続き、寂しさの解剖について。この1年ぐらいの間にぼくに起こった大きな変化の一つとして、寂しいという感覚が薄れ、その代わりに、自分にとって大事な人たちと深くつながれている感覚が当たり前になっているっていのがあって、それについて書こうと思ったんだけど、今日はその前の前ぐらいの段階について書いていく必要があると思ったので、ぼくの昔話をしようかと思います。
※今メルマガを書き終わってから再度ここを書いてるんですが、今日はいつもに増して鬼長いです。なので、「心から信頼できて満たされた人間関係を今より増やしたい」って思う人以外は、今日のは読まなくていいです。逆に、その辺について、何かピンとくることがある人は、何日かにわけてでもいいので、一回全部読んでみてもらえると嬉しいです。
何でも話せる相手がいない人の2つのパターン
そもそもなぜ、人間関係について取り上げようと思ったかというと、満たされた人間関係を作れている人の方が、長期で見るとビジネスがうまくいく確率が高いんじゃないかと思ったからなんですけど、「どんなことでも腹割って話せる相手がいますか?親友でもパートナーでも」って聞いたときに「前はいたんだけど今はいないです」っていう人がまあまあいるもんだなってことに気づき。なので、そんな人は、ビジネスのことをゴリゴリ進める前に、パートナーか親友を探した方がいいんじゃないかと思ったわけです。
ただね、これがなかなか難しい。なんでかって言うと、昔から今に至るまで「隠さずになんでも言える人は親を含めていない」って人は、そもそも親友みたいな存在がどうやったらできるのかをわかっていない。ちなみに、過去のぼくもそうだったので、それについては後ほど。そして、親友のつくり方がわからない人は、親友なんて必要だと思っていない。心の底では本当は求めてるんだけど、意識的には「そんなのいなくても生きていける」って思ってることも多いんだよね。人は望んでたけど手に入らなかった経験が多いと、それを手に入れるのは難しいって思うようになってくるんだけど、難しいってそのまま受け止めちゃうと自分がダメだっていう烙印を押しちゃうことになりかねないから、「難しい」という認識を「自分には必要ない」って認識にすり替えるんだよね。そんなことよりも大事なのは「仕事で成果を出せてるかどうかでしょ」的な、自分が得意なことにすり替える。それによって自分を守る。過去の自分もそうでした。
そしてもうひとつ、過去には親友がいたけど今はいないってタイプ。これは学生時代に親友だった子がいるけど、結婚しちゃって疎遠になっちゃったとか、引っ越ししてからほとんど会わなくなっちゃったみたいなケースが多いんだけど、この場合は親友というのは「たまたまできた関係性」なんですよね。学校っていう、良い意味でもよくない意味でも人間関係に対する期待値調整がちゃんとできてない青春時代において、毎日顔を合わせることによって自然と次第に仲良くなっていて、とにかく多くの時間やときには秘密なんかを共有したことによって親友になったっていうケースね。でも、このタイプは意図したわけじゃなく偶然親友が見つかったので、親友をつくりたいと思って意図的に親友をつくった経験がないし、そんなことができるとも思ってない。たとえば職場で毎日顔を合わせる人がいたとしても、ある程度のビジネスライクな付き合いの部分も多いので、学生時代みたいな感じで親友になっていくみたいにはなりづらいわけですよね。じゃあ、あのときにみたいに日々なんでもあったしょーもないことをお互いLINEしあったりね(ぼくらの時代は当然まだLINEはないが)、困ったことがあったら長電話して相談したりね、ストレス発散で一緒にカラオケ行ったり旅行に行ったりね。そんなことができる相手がいるといいなーと思うけど、そんな相手は今さらどうやったらつくれるのかわからない。このタイプは、そう思ってる人が多いんじゃないかなーと思うんですね。
でね、先にぼくの個人的な考えとして結論を先に伝えておきますが、
- ほとんどの人にとって親友でも配偶者でも同僚でもどんな関係でもいいけど、なんでも話せる相手はいた方がよくて
- かつ、意図すれば大人になってからでも親友をつくることができるけどそのときに大事なのは「勇気」である
ってことだと思ってます。この結論的話はまた後で。その前に、ぼくが20年近く人間関係に悩んできた経験について話すことは、ある1人の実例としてイメージしやすいんじゃないかなと思うので、それについて書いています。
今のぼくを知っている人は、ぼくが人間関係でそんなに悩んでいたなんてことは想像もできないと思う。それぐらい充実した人間関係には相当恵まれているから。ただ、昔は全然そうじゃなかったのね。それには、よくある原因と、特殊な原因がありまして。
9歳までのぼく、9歳からのぼく
9歳、小学校3年生っていうのは1つの分岐点とされることが多いんでしょうか。思春期の入り口的なね。ぼくの場合も、自分の性格的な変化の分岐点は9歳でした。めちゃざっくり言うと、9歳まではものすごく元気で根明でよくしゃべる性格だった気がするんですけど、10歳からちょっとずつ内向的というか内気というかな性格に変化していきちょっとずつ心の中に闇を抱えるようにもなっていったのかなと思います。
まずぼくが人間関係に悩むようになった「特殊な原因」の方について書くと、何度かメルマガに書いたことがあると思うんですが、ちょっと変わった家庭環境に育ったからです。端的書いちゃうと
- ものすごく短期でキレるとめちゃくちゃ怖い父親
- 父親の猛反対のもとで「エホバの証人」っていう宗教を熱心に信仰し、(父親が反対しているので)隠れて子どもたちにもその教義を教えている母親
ってことが、多少の特殊性がある家庭環境の要因です。それ以外でも貧乏でお小遣いをもらったことがないみたいなのも関係してくるんですが、それよりも上の2つのことが大きいんですね。で、そんな状態なので、家では両親がめちゃくちゃ喧嘩してることは多かった記憶があるし、父はキレると母に暴力を振るうことはよくあったので、いつも父の顔色を伺いながら過ごす家庭だったんですね。
誕生日を祝うのは禁止。他にも…
で、ただそれよりも大きかったであろう影響は、エホバの証人の教義で、いろんな細かいルールがあるんですね。たとえば
- 〜おめでとうと言うのは禁止。なのでうちでは誕生日におめでとうとは誰も言わないし、ハロウィンもクリスマスもないし、元旦にあけましておめでとうございますも言わない文化
- ご飯を食べるときに「いただきます」と言ってはいけない(上の派生形かな)。なので学校でもいただきますのときに自分だけ手をあわせなかった
- 国家敬礼のときに国家の方を向いてはいけないので、右向け右とかって学校でなったときに、自分だけ先頭を向いたまま
- 校歌や君が代は歌わない
- 基本的には同じエホバの証人の子以外と遊ぶのは良くないとされているから放課後、そうじゃないほとんどの学校の友だちと遊びにいくのは禁止か制限されてる
- TVもゲームもマンガも教義からして禁止
みたいなことがありました。0歳のときから母親からその教義を教えられてるから、それが世界だと思っているので、母親がいない学校でも神様が見ているし、その行為を破るのはよくないって強烈に体に染み付いているので、学校でもその教義的ルールに従って行動してんたんですね。物心つくまでは特に。
じゃあ、それが何を意味するかっていうと、学校とかで話をするってなったら大体昨日見たテレビとかゲームの話でしょ。で、そういうのは禁止されてるから話についていけない。そもそも放課後、みんなで遊びに行こーってなったときに、自由にはいけないから「小さい頃に友だちと遊んだ経験が圧倒的に足りない」わけなんですね。これは後々じわじわボディーブローのように効いてきます。
ただね、最近意外なことに気づいたんですよ。ぼく小さい頃の記憶があんまりなくて、やっぱりすごいつらい思いをしてたらそれを思い出さなくて済むように、記憶がなくなるっていうのはよくあることなので、小さい頃からそうだったのかなーと思ってたんですけど、なんか違うんじゃないかなーと最近思って。でね、昔のことを思い出してみると、小学校の1年とか2年のときとかは、仲良かった(同じ宗教じゃない)友だちと川に泳ぎにいくみたいなのを、おかんに車で連れていってもらってた記憶があったりして。だから、エホバの証人以外の友だちと遊ぶのは基本禁止の方向だったけど一律にすべてダメって言われてたわけじゃなく、ある一定の割合はそうじゃないけどこれぐらいならまあ仕方ないかって感じで、母のさじ加減で許されてたような気がするんですね。で、このときのことを思い出すと、友達に「学校終わったら川に遊びに行こう」ってなんの気兼ねもなく誘ってたような感覚があるんですよね。そして、このときは友だちともつながっている感覚があったような気が最近になってしてきました。
そして同じことは家にも言えて。両親が喧嘩してるのはめちゃくちゃ心が痛くて嫌だったし、おとんが怒ったら怖すぎるけど自分は何もできないからがんばって時が去るのを待つしかないし、できるだけ怒らせないようにしようっていうのを意識してるのも事実だったと思うんですけど、家で怯えるように過ごしてたかっていうと全然そんなことはなくて。おとんのことも好きだったしおかんのことも好きだった。このときはまだ家にお金があったから、家族で月1外食でステーキハウスみたいなところに行くっていう習慣があったりして、そこでバイキングのコーナーにライチがいっぱいあって、それを山ほど食べるのが好きだったなーとか。家族で今日はボーリング行こうってなったけど、おとんが朝からビール飲んで予想通り寝ちゃって行けなくなってすごい残念な気持ちになったりとか。だから普通に家族でたまにどっかにご飯を食べにいくとか、遊びにいくとかっていうのがすごい楽しみで。そういう風に両親が喧嘩してなくておとんも機嫌がいい平穏な日には、愛情も安心も普通に感じれてたんじゃないかなと思って。とにかく「普通ではない」特殊性が多少ある家庭環境には育ったけど、9歳まで根明で学校でいきいき過ごしてたのは、安心があったんじゃないかなーと思ったんですね。
●●がきっかけで安心が失われていった
じゃあ、なぜそれが9歳を境に変わったのかというと、これは「よくある原因」の方ですが転校です。小学校3年生の2学期に転校したんですけど、それがきっかけだったと思うんですね。このときのことも細かくは覚えてないけど、超断片的にうろ覚えしてるのは、前までの学校のようになんかの遊び(たとえばドッチボール)をしてるときに「ぼくも入れてー」って言ったときに、クラスで一番の人気者だった内田くんって子が「ダメ」みたいなことを言ってきたようなことがあったんですね。うろ覚えですが。で、担任の米澤先生に、「内田くんが、仲間に入れてくれないので先生言ってください!」って頼みに言ったら、「そういうのは自分で言って仲間に入れてもらうのよ」って言われたような気がして。全然覚えてないけどね。で、女性で結構太った体型でよく起こる米澤先生のことが、めちゃくちゃ嫌いになったような気がしてます。なんか書いててもムカついてきた!!!笑
まあでもあったっていうのは、そんな感じで多少仲間はずれにされることがあるぐらいで、いじめられるほどのことはなかった。でも、みんなが楽しそうにドッチボールしてるのを教室でいいなー、どうやったら仲間に入れてもらえるんかなーって見てたような気もする。全然覚えてないけど。でも、小学校5年ぐらいのときに急にモテ期が到来して、クラスのかわいいって人気だった女子数人から同じような時期に告白されてってことがあったことを考えると(これはいい思い出だからかはっきり覚えてる笑)、そこまでまだ隠キャにはなってなかったんだろうなーと思います。クラスの中でメインの集団には入ってないけど、かといって隅っこの感じでもないと。でもまあ転校する前の、これまでだったら何の気兼ねもなく「遊ぼー!」って言って「うん、行こー!」って言われてた当たり前が、転校後は当たり前じゃなくなった。だから、遊ぶということに1つ超えるべきハードルができた。誘っても断られることがあるんだ。仲間に入りたいっていっても入れてもらえないってことがあるんだって感じたんだと思います。まあ、そんなことは社会性を身につけていく上では普通のことなので、転校してなくても同じ時期に経験した可能性もありますけどね。
このタイミングで、本当は親に相談とかできたら変わってたのかもしれないですね。でも、思春期に入ってからは親にそういう相談をしたいって思うことはなくなった。理由はなんでか覚えてないけど、相談することが恥ずかしかったのか、なんなんだろう。
中学の頃からちょっとずつ心に闇が…
そうやって転校して、これまであった安心感が当たり前でなくなり、それに合わせて状況をしっかり見て空気を読んだ言動をするっていうことをちょっとずつ覚えていったんだと思うんですけど、次に中2のときにもう1回転校したんですね。で、そこはより田舎の地域になって、今まででは考えられないぐらい治安が悪くなったんですよ。だって、投稿初日に、廊下をバイクで走る不良がいたんでね。こわいこわい。これは目をつけられたら終わるなと思って、できるだけ目立たないようにしようって思って、さらに目立たないように気をつけながら、状況を観察して自分の立ち位置や言動を決めるっていうのが強くなったんだと思います。
この辺から、ちょっとずつ心に闇に出てきてた実感があります。それは学校で仲良くる友達の傾向に出てた。心に闇を抱えてそうな人のことがどうしても気になってしまう。すごい明るくてって子じゃなく、闇を抱えてそうな子や斜めから見てる子の方が話してて気が合う感じがする。じゃあ、その闇はどこから来てたのかっていうと、家で両親とつながれてない感覚からきてたのかなーと思うんですね。9歳までのときは家にあった安心感や愛情を感じるってことが、中学あがってからぐらいからは少しずつ感じられなくなっていってた。ぼくは三人兄弟の長男なんですけど、父は三男に野球を教えるのにかかりっきりで、ほとんどコミュニケーションを取ることはなくなってて。で、母は次男にエホバの証人の教えを共有するって関係で、ぼくは中学にあがる前後で「自分はもう学ばない」って言って、母親に泣かれたけど宗教の集まりにいくことだったり研究の時間(母が教えを共有する時間)もとらなくなってたので、そういう意味で、これまで宗教の教えを共有することによって存在してた母親との定例のコミュニケーションが減っていたってこともあるんだろうと思います。
自分を取り繕って人と仲良くしてた時代
人との関係において、心の中で距離を置くようになったのは、特に高校1年で不登校になってからです。不登校になってるのには自分の中で理由はあるわけですが、まわりの友だちはそんなことは一切考えてないわけですよね。なので、自分とその子たちは全然違うってのをよりハッキリ認識するようになった。ときどき学校にいくときは、ぼくも普通に楽しそうにコミュニケーションを取るわけですけど、心の中では闇を抱えていて、そんな闇は誰も興味を示さないだろうし、そもそもみんなの中にはないもの。だから、一生懸命自分を取り繕って、表面的には仲良く楽しくコミュニケーションをとっていました。
で、こういう人との関係性の作り方っていうのは、大学を卒業するまで続きます。自分がお金がないからみんなみたいに服が買えないことや、そもそも服のブランドの話にまったくついていけないこと。友達がドトールでコーヒー飲んでるけど、そのお金の使い方がもったいなすぎると感じ、自分はそんなお金があったら自分の成長に使って将来お金に困らないような状態になりたいと考えていること。親がエホバの証人で自分もその教えに従って生きてきたから、今でも誕生日でおめでとうって言うたびにほんとに言っていいのかなってドキッとしたりお祝いすることに慣れないこと。自分は影では冷たいやつだとか人から悪口を言われてるんじゃないかってときどき不安になること。そういう「人には打ち明けられないたくさんのこと」を胸に隠し持ちながら、表面的には友だちとして仲良くするっていう人間関係の作り方をしてきました。能力的には人から尊敬されることが多かったけど、それが逆にみんなとの距離を感じさせる。アイツは違う、おれたちと一緒じゃないと思われる。ほんとはみんなと仲良くなりたいのに。だから、ずっと人間関係については自信がなかったんですね。小さい頃に友だちが大体みんなやってるテレビを見るとかゲームをするとか一緒に服を買いに行くとかって経験が少なかったから、「友だちとの遊び方」がわからなかったんだろうなと思います。
そして、仲良くなるためには、みんなに自分のことを注目してもらうのがいい。そう思っていい成績を取ったり、部活でやってる活動で優勝をし続けたりしてたけど、自分がすごくなって注目されるのは最初だけで、今度はその分野で努力すればするほど、友だちと遊ぶ時間は減るので孤独を感じる。だから、自分が本当に求めているもの(心から安心できて満たされる友人関係)を手に入れるための効果的な行動の仕方がわからなかったんだなと思います。
トビとの飲み会で衝撃を受けた
社会人に会って1年目。ぼくはトビという関西出身の知り合いと東京で再会します。トビはぼくが大学4年生で学生団体をやってたときに、企業から協賛を求めて営業してたときにアポでいった先で初めて出会った人。「こんなんじゃあお金を出せないですよ」ってこっぴどくダメ出しされたことから、すごい印象に残ってた。そっからどういう経緯で次につながったのかはわからないけど、すごいオーラをまとって営業課長か何かって名刺に書いていた彼は、大学を中退してすでに会社で勤めていたぼくと同い年だってことが、あとでわかったと。同い年だけど、入社してものすごい結果を出してこの年ですでに役職についてると。すごいってことはもうオーラでわかる。同い年でもすごいやつがいるなーと思って尊敬しました。
大学4年生の初対面から次にどうやって会ったのかは覚えてないんですが、ぼくも就職して社会人として東京に出てきた1年目。何かのきっかけでトビとコミュニケーションを取ったら、東京に出てくることになったって話になったんだっけな。このときはまだそんなに仲良くなかったけど、ぼくは営業でいろんな人との人間関係が多少できてたので、「トビ、じゃあ東京に出てくるんだったら知り合い少ないよね?じゃあ同い年ぐらいで東京で知り合ったおもしろそうな人紹介してあげるから、トビを囲む会をやろう」みたいなことをぼくが提案したような気がします。
でね、その初回でのトビを囲む会でのことなのか、次の飲み会では覚えてないけど、トビとの飲み会でぼくはものすごい衝撃を受けたんですね。それは何かって言うと、トビが初対面の人に自己紹介で、普通だったらそんなことを言わなくいいよねってことまで自己開示をしてた。そして、他の人それぞれに本当に興味を持って話を聞いてた。ぼくも、営業だったんでね、初対面で仲良くなるっていうことはスキルとしてはそれなりにできたんですけど、それとは全然違う感じ。とにかく初対面から、ここまで心を開ける人ってのを初めて見た気がしたんですね。
で、例に漏れず、ぼくにも初対面とは言えないぐらい、ぼくの背景とか今考えてることとかをいろいろと根掘り葉掘り聞いてくる。で、「そんなことを考えてるってやまけんってほんますごいよなー」とか言って褒めてくれる。ぼくがいないところで、他の人にもぼくのいいところを話してくれてるみたい。
そのとき、これって何なんだろう?って思ったんですよ。そのときのぼくはまだ「人には打ち明けられないこと」「打ち明ける必要がないこと」は自分の中に隠し持った上で、人との関係性を築いてたんでね。こんなに人に心を開くって普通ないよなと。これは怪しい!きっと仲良くなった先になんかを営業して買わせようとしてるんじゃないかって疑ったんですよ。それぐらいぼくは斜めから見てたんですね。人のことを根本では信用してなかったんだと思います。
「親友の作り方」を見せてもらった
で、こっからはぼくの変なところなんですけど、これは怪しいから調査しないといけないって思って、何回か飲みを開いて様子を見るものの、いつもどんな人に対しても心を開いて接してると。これは、もっと調査するしかないと思って、「一緒にルームシェアするぞ」って言って、一緒に住み始めたんですね。だって一緒に住んでたらさすがに裏があったらボロが出るでしょ。で、住んで見たら、やっぱり変わらなかった。
そのときにぼくは、やっと気づいたわけです。人に対して本音で付き合うかどうかってのは「本人が選択」できるんだなと。人に対して初対面からでも心を開いていくように生き方。自分を隠さずに曝け出していくというあり方。そういう生き方ってのがあるんだなと初めて知ったんですね。じゃあ、自分はどうしたいのか?ってのを考えたときに、それはもう心の奥底では飢えてたんですよ。本音でつながれる関係、ありのままの自分をさらけ出せる相手、それでいて自分のことを認め理解し、応援してくれるような関係。そして自分も同じように相手のことを尊敬できる、相思相愛の人間関係が本当はほしいと思いながら、それは普通の人にはできても自分みたいに心の奥に闇を抱えた人間にとっては難しいんじゃないかと思ってたわけです。そしてどうすればそういう関係を自らつくっていけるのかも知らなかった。
ぼくはトビっていう人と出会って、「そういう世界がある」ってことを知ったんですね。で、そのときから、ちょっとずつ心の闇は小さくなっていきました。例えば、実は親がエホバの証人でっていう過去も、普通に生活してたら言う必要がないから言ってなかったわけだけど、それを言うことにすごい抵抗があったんですよね。そういう家庭環境で育ったことがコンプレックスで、人にそれを伝えても理解されないだろう、むしろ変なやつだと思われるんじゃないかと思ってたわけです。でも、自分が自己を開示するかどうかは、自分の選択によって選べるんだってことを知った。そこから、今までは抵抗があって人には打ち明けてこなかったことを、ちょっとずつ頑張って人に言ってみるようにした。もちろん誰彼構わずじゃなく人を選んでね。この人とは仲良くなりたいなって人に対して、自分から心を開く、自己開示するっていうのをやってみるようになった。そうするとね、「こんなことを言ったら人にどう思われるんだろう?」ってことがものすごく怖かったんだけど、いざ自分が話してみると相手の反応は別に思ってたものと違った。なーんだ、こんなものかと。で、そこから今まではなんか得体の知れないこわさがあって人には隠してことを。ちょっとずつそういうやって言うようになってくると、同じ話をするときに前は超ドキドキして手に汗握る緊張があったのに、だんだんと慣れてきて何事もないかようにふつうに話せるようになっていった。要は慣れだなと。
そして、隠してたものを隠さなくなることは、こんなも自分を軽くしてくれるものなのかということを知りました。そうやっていくうちに、「基本人は自分のことに興味がない」「人は自分のことを理解してくれない(できない)」っていう偏った前提をも修正されていきました。1人の親友との出会いによって、生きるのが相当楽になりました。自分の能力や実績に対しての興味ではなく、「自分という人間そのもの」に興味を持ち続けてくれるっていう人がいるっていうことがどれだけ安心感につながり、またこの安心感があるかどうかで自分の中から湧いてくるパワーの量が全然違うんだってことをこのときの経験で初めて知りました。
大人になって親友をつくるときに意識してみるといい6つのポイント
自分が素の自分でいられる相手。自分がダメなところも見せることができるし、それも受け入れてくれるという安心感が持てる相手。こういう相手が1人でもいたら強いです。それが親でも、配偶者でも、親友でも同僚でもね。でも、もしそういう人が1人もいないとしたら、そういう人をつくる努力をすることは、人生においてもビジネスにおいてもものすごく意味があることなんじゃないかと思います。
でも、大人になってから親友をつくるってのはやっぱり難しいですよね。じゃあ、どうすればいいのか?ぼく自身の経験や、これまでぼくが関わった人にアドバイスして効果があったことなどを踏まえて、いくつかのポイントを書いておこうかと思います。
1、親友をつくろうという意図と見つける努力は必要
ビジネスを始めるときに待っていてもお客は来ないように、親友も待っているだけだと偶然にできる確率は低いです。現状で何でも話せる人が多い人ほど、あまり意識してなくても親友的な関係の人は増えいやすいけど、現状で親友的な関係の人がいないとか少ない人ほど、待っているだけだとそういう関係の人はできないことが多いんじゃないかと思います。なのでまずは、彼氏彼女をつくろうと思ったら、人に紹介してもらったらマッチングアプリをしてみたり、とにかく新しい人に会ってみる機会を増やすことをやると思うんですが、それとまったく同じです。ほんとうに仲良くなれる人は、どんなところにいるんだろうって考えて動いてみる。それは交流に重きを置いたオンラインサロンかもしれないし、自分の趣味に関連するコミュニティに入ってみることかも知れない。周りの人で多くの知り合いがいて飲み会とかをやっている人がいたら、そういう会があったら誘ってみてほしいってお願いしてみるのもひとつかもしれないです。とにかくまずはいろんな人と会ってみる機会をつくるのがスタートです。内向型の人だと新しく人と会うのはものすごく億劫だし疲れると思いますが、一定の期間はがんばってやってみるといいと思います。
2、コミュニティなら集まりがあったらいっぱい顔を出す
人と仲良くなるために一番簡単な方法は、とにかく何回も会ってみることです。コミュニケーションが得意じゃなくても会っていくと多少打ち解けやすくなりますよね。だから、集まりの場が本来苦手な人でも、新しい人間関係をつくろうという時期は、人が集まる場に出向く優先順位をあげた方がいいです。最初は居心地が悪いだけで、何の実りもなく疲れて帰っただけってなることもあるかと思うんですが、だんだん足を運んでいくうちに慣れてきます。その場での自分の立ち振る舞い方もそうだし、自分がどんな人とは合いやすくて、どんな人とは合いにくいのかとか。なので最初だけは食わず嫌いせずに、あるコミュニティで集まりがあったらできるだけいっぱい顔を出してみるのがいいと思います。
3、1対1で話す機会をつくる
次は、自分がこちらから仲良くなりたいなと思った人、または相手が自分に興味を持ってくれて仲良くなれそうな人と、1対1でゆっくり深く話すのがポイントです。人が結構いる飲み会みたいな場だと、みんなでわいわい話すっていうことが多いですよね。ただ、今言っているのは、浅い知り合いや友だちを増やす話ではなくて、1人でもいいので何でも話せるような親友をつくることです。なので、飲み会の場で1対1でゆっくり話せる機会があったらそれでもいいし、そういうのが難しそうだったら「また今度一緒にご飯(お茶でも個別でzoomでも)とか行きたいです」って軽くジャブ的に誘ってみて相手が反応が良さそうだったら、後日メッセを送って日程調整する。そうやって、1対1で会う場を作ることが大事です。
4、できる範囲で自分から心を開いてみる
1対1で話してさらに深い話ができたら、そうでもなかったなーって思うケースとやっぱりこの人好きだなーっていうケースとわかれるじゃないですか。デートと一緒です。で、さらに仲良くなりたいなと思ったら、自分から何かに誘ってみたり、会ったときに自分からちょっとでもいつもより自分をさらけ出すってことにトライしてみれるといいですよね。ただ、自分は相手と仲良くなりたいと思ってるけど、相手からの反応が悪くてなかなか日程が決まらないとかね、そういう一方通行的になってそうだなーってことはあるじゃないですか。これもデートと同じで。そんなときは深追いせずに、ネクストトライって感じですよね。結局のところ、親友っていうのは、双方向の関係性なんでね。自分が相手のことに興味を持ち好きだと思っているように、相手も自分に対して興味をもって一緒に過ごすのが楽しいって思ってくれてないと意味がないんでね。
5、答え合わせをする
これまた恋愛と同じですけど、距離が近づいてくる方がこわさや不安が増えがちです。だって大切だと思ってる相手から拒絶されるとショックが大きいからです。でもここが不安だからってそれをそのままにしていると、親友の関係にはなれないですよね。なので、それはタイミングを見て、何か気になっていることがあったら、「〜に対してぶっちゃけどう思う?」みたいに自分から切り込んでみるっていう勇気が必要なことも多いです。実際に相手がどう思ってるのか、何を感じてるのかを聞かないと、どんどん不安になっていくし、不安を埋めるために相手に嫌われないような行動を取るようになっていっちゃったりするんでね。なので、ここが一番勇気がいることですが、不安を感じることがあったら、タイミングを選んで勇気を出して「相手に実際の気持ちを聞いてみる=答え合わせをする」っていうことが大事かなと思います。
6、みんな(その他大勢)と仲良くなろうとしない
自分が心を開ける相手ができてくると、というかそういう親友的な相手を作っていくためには、自分にとって数少ない大切にしたい人間関係と、それ以外の人間関係をちゃんとわけることが大事です。親友的な人をつくることが苦手な人は、八方美人的になりがちなんですね。意識が「みんな」にいっちゃってる。みんなに嫌われないようにしよう。ダメなやつだと思われないようにしようとかね。でも、みんなっていう不特定多数への意識が強ければ強いほど自分の中にはいつも不安が存在することになります。逆に相手がどういう価値観を持っているのか、自分のことをどう思ってるのかみたいな「心のうちが読める」人で不安を感じなくて済む人と一緒に過ごすことやコミュニケーションをとる機会が増えることによって、安心していられる時間が長くなり、その分自分の心のエネルギーチャージがなされるようになるわけですよね。自分がこの人とはこれからも深く関わっていきたい人とそうじゃない人はわけて捉えられた方がいいと思います。とくに満たされた人間関係が少ないうちは特にね。
ということで、超絶長いメルマガを書いてきましたが、今回最後まで読んでくれた人は相当少ないんじゃないかと思います(笑)。冒頭にも書きましたが、今回の人間関係編は、多くの人にとっては当たり前のこと過ぎて、または興味関心が薄くてそこまで読みたい内容じゃないかも知れないけど、本当に信頼して心をかよわせられる人がいなくてものすごく孤独感を感じてた学生時代の自分みたいな人とか、そうじゃなくても何かしらもっと深い人間関係を築いていきたいって人がもしメルマガ読者の中にちょっとでもいるんだったら、そういう人に必要なメッセージが届くといいなと思って、全力でぼくが書けることを書いてみました。
なので、今日も何か感じたことや気づきがあれば、ぜひ気軽に返信してもらえると嬉しいです。「最後まで読みましたよ!」とか「長かったです!」とか「おもしろかったです!」ぐらいの簡潔さでもいいんで。みなさんからの反応が書く力になってるので、良かったと思った人はなんかリアクションもらえると非常に励みになって嬉しいです。
次回は、直近1年でぼくの中から寂しさがなくなっていったのは、何がそうさせたのか?ってことについて自分で自分を分析して考察したいと思います。
では、また!
<全3シリーズ>
Vol.1「寂しさの解剖」
Vol.2「大人になってから親友をつくる勇気」←本記事
Vol.3「寂しさからつながりへと日常的な感覚が大きく変わったことについて書けることを全部書いてみた」

天才研究家やまけん(山田研太)が「アート型ビジネスの考え方と実践方法 」や「最新の天才研究事例」などについて不定期で書いているメルマガです。
他にはない独特な長文芸にある種の中毒性があるとかないとか、噂されるそんなメルマガで、7,000人以上の人が購読してくれています。
特に、アート型ビジネスについては実際のプロデュース事例を含めて、かなり具体的に解説していることも多いです。なので、SNSでの発信よりも、より濃ゆいやまけんの発信を見てみたいという方はぜひ登録してみてくださいね。