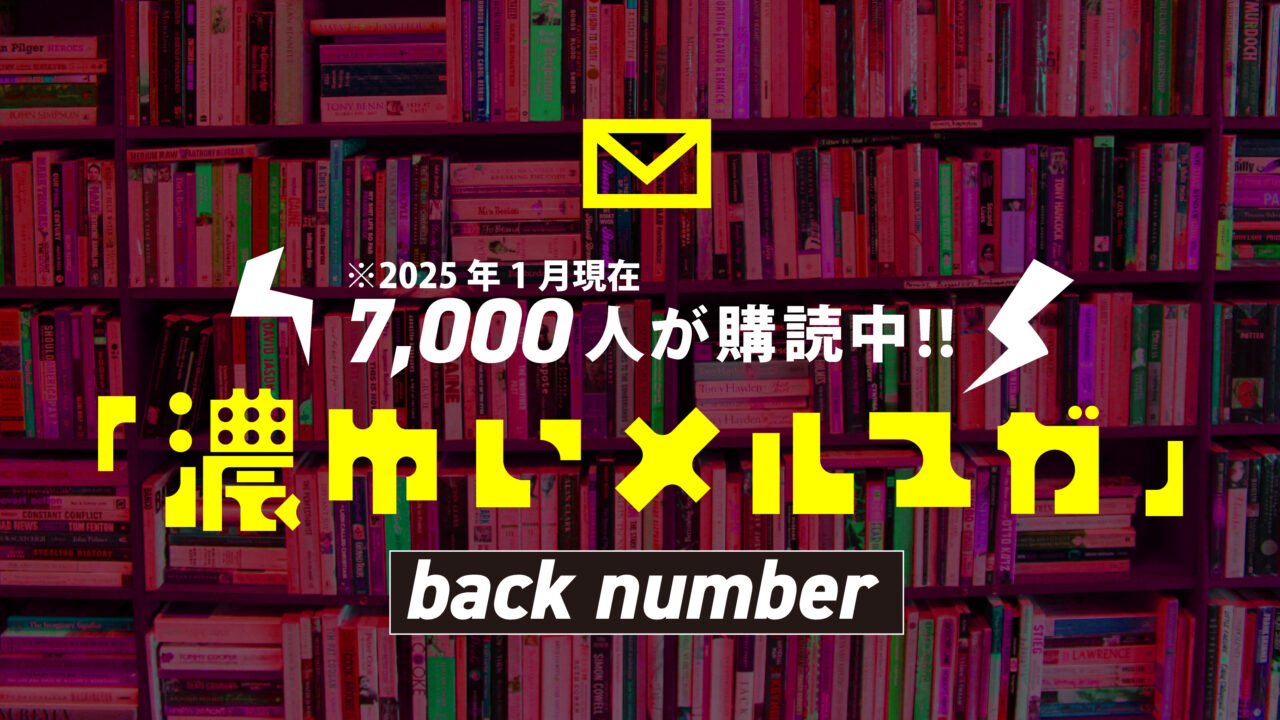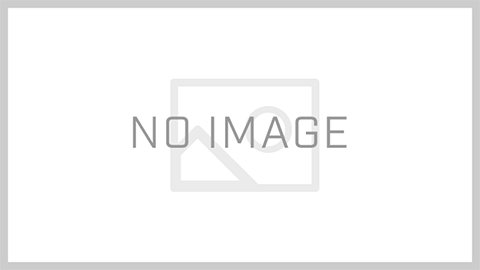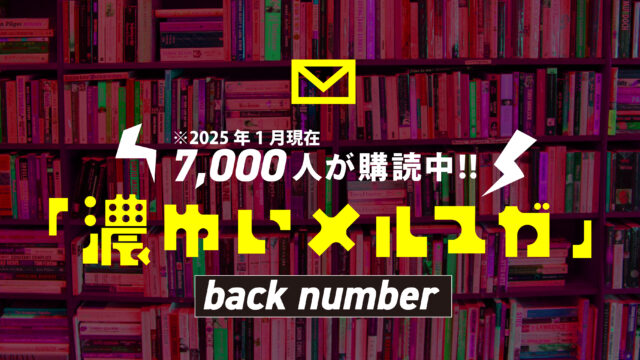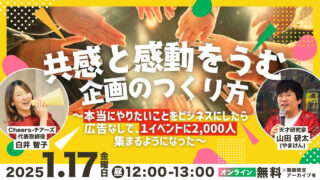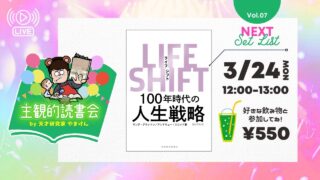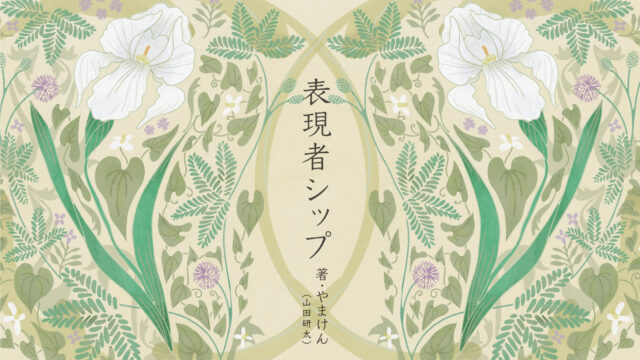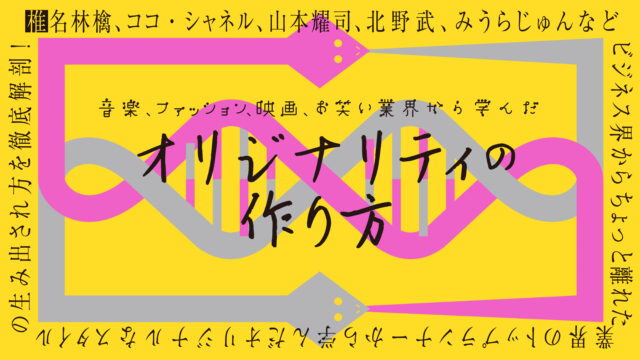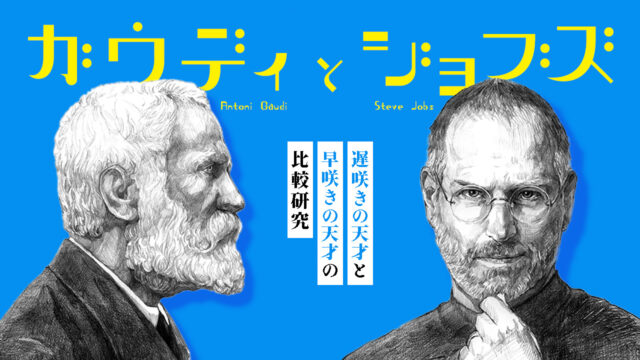この記事は、ぼくのメルマガのバックナンバーです。メルマガでは、「最新の天才研究についてや、ぼくがプロデュースを手がけるアート型ビジネスの最新事例など」について書いています。他にはない独特な長文芸にある種の中毒性があるとかないとか、噂されるそんな不普通のとはちょっと違った『変なメルマガ』です。メルマガはこちらから無料で登録できます。
通常はバックナンバーは公開してないですが、メルマガに登録しておくと本記事に転記されているような内容を全部で読むことができます。
【以下転記】2023/3/5のバックナンバー
※全4シリーズのVol.3です。
————————————————————————————————
こんにちは、やまけんです。
これまでの続きです。前回までのメルマガを読んでない人は流れがわからないと思うので(そして割と短くてサラッと読めると思うので)こちらからどぞ!
vol.1「人生で一度も「楽しい」と感じたことがない男の物語」
https://yamadakenta.jp/4961/
vol.2「クララが立った。」
https://yamadakenta.jp/4638/
では、今日の分、はじまります。
・・・
アート合宿の2日目の午後のあるワークで、クララが立った。ぺーさんは、そのワークをしている最中に、人生で初めての感じる感情が自分の中に生じていることに気づいて驚いた。「”楽しい”っていうのはこういう感覚かぁ!今は、すごい楽しい感じする」
一体、何がぺーさんをそうさせたのか?今日は、ぺーさんに具体的に何が起こったのかを、アート合宿初日の流れから見ていこうと思う。
まずアート合宿の初日には、その予兆はなかった。初めて出会った人がいっぱいいる初参加のプログラムにおいて、ぺーさんは、いつも通り自然と身体を緊張させ、居心地の悪さを感じていたからだ。
ちなみに、アート合宿というのは、ぼくが主催の一人として企画したもので、画家の峻ちゃん(中村峻介さん)がメインでその場をファシリテートするプログラムだ。このプログラムは一風変わったもので、アート合宿という名前ではあるが、参加者は峻ちゃんから「絵の描き方」を教わるわけではない。あえて言うなら、絵を描くというひとつの手段を使うことによって、日常よりも深く深く自分に向き合うということを体験するプログラムだ。山梨の自然に囲まれた環境で、好きなタイミングで温泉につかったり、美味しいご飯を食べて過ごすという意味では、「リトリート」的な要素を多分に持ち合わせたプログラムであり、絵というツールを使った「ユニークな内観プログラム」ということもできるかもしれない。
初日の最初に、峻ちゃんは参加者にみんなにこう伝えた。
「このプログラムの最中は、できるだけ”赤ちゃんでいる”みたいな感覚を大事にしてほしいんですね。自分にとって心地よいことをあえて選択する。だからいつでも外の空気を吸いたいなーと思ったら外に散歩に行ってもらってもいいし、眠たいなーと思ったら部屋に戻って寝てもいい。それぞれが、自分の欲求に従って、自分を正直に満たしてあげるってことを大事にしてほしいと思います」
この言葉を聞いて、30人ぐらいの参加者の何人かは肩の力が抜けるのを感じ、何人かは今回の4日間はあえて自分を甘やかしていつもより自由に過ごすってことを意識してみよう、という風に感じたりした。
じゃあ、このときにペーさんはどうだったかということ、頭では言われたことは理解できてるけど、正直まだピンとはきていない。赤ちゃんみたいな感覚っていうのがまだうまく想像ができなかったからだ。あとは、「自由にしていい」っていうのは、ある人にとってはとても嬉しいことかもしれないが、ぺーさんにとっては苦手な方に入る。やることが決まっていて明確な方が安心するからだ。
じゃあ、ペーさんはなぜアート合宿に参加しようと思ったのか?それは絵に興味があったからでも、絵を描くのが元々得意だからなわけでもない。むしろその逆だ。アート合宿への申込動機にペーさんはこう書いていた。
これまで価値がわかりやすい技術系や経営系のセミナーにたくさん参加してきました。アート合宿はこれまでの自分が参加するもので一番縁遠いものだと感じたんですが、やまけんさんの発信を見ていて、アート合宿のような自己を見直す、というよりも解き放つ、許すようなものが必要なのではないかと感じ、参加を決意しました。
これまでアートは見るもので、自分でやるものじゃない、むしろ美術の授業でずっと最低評価だったのでやってはいけない、と思ってたので楽しみにしています。
絵はむしろすごい苦手だけど、自分を見つめ直すためには必要じゃないかと思って参加を決めた。
・・・
アート合宿の初日に峻ちゃんが意図していることにひとつは、参加者がこれまでの人生の中で思ってきた「絵を描く」という行為に対するイメージを、体験を通して無意識的に手放すことができること。つまり、絵に対して「上手いか下手か」という評価軸で、自分の絵も人の絵も見てしまうものの見方が、自然とアンインストールされるような場を作る。そうすることによって絵を描くという行為が、苦手で自信がないものから、もっと自由で親しみやすいものに変わりやすくなる。
参加者はまず、自分が好きな色を自由にパレットに取っていいですよと言われ、「どの色をパレットに乗せるかな」っていうのを考えて少し気持ちがあがる。また、小学校のときには使ったことがないような大きな絵の具のチューブから、自分のパレットに絵の具を絞り出すときに、ぐにゅぅぅってなる感じが、新鮮な身体的感触を伴い、それでまた気持ちが少し上がる。
それぞれが好きな絵の具をパレットに出し終わってから、(どういうワークから始まるかは峻ちゃんのインスピレーションによって毎回違うが)例えば、「自分の今の気持ちや体の感覚を、この一番小さいサイズのキャンバスに出してみましょう」というテーマが与えられる。最初からいきなり写実的な絵を描くと、どうしても反射的に上手い下手の感覚が頭の中にあがってきてしまいがちだが、気持ちや感覚をそのままキャンバスに落とすとなるとどうしても抽象的にならざるを得ないし、「自分の気持ち」を絵で表現してみるだけなので上手いも下手もない。また自分がいきなり「描きたいものは何か」と広すぎる選択肢の中からテーマを決める必要もない。
こういう風に、できるだけその人が、自分や他人や物事をジャッジする思考が入ってきにくいようにして、低いハードルから「絵を描く」という行為に入っていけるようにリードするのが峻ちゃん流だ。ここでは詳しく書かないが、彼の今のあり方を作っている大きな原体験は、ネイティブアメリカンの儀式に参加したときに自分がより強く本質的な自分を感じられた経験からきているので、「その人がその人であれる」ということを何よりも大事にしている。絵はあくまでもその手段というスタンスだ。
ちなみにぼくは人からときどき、「仙人みたいですね」と言われることがあるけど(多分世間的な評価や売上を負わず、我が道をいくっていう感じで天才研究をしてるからだと思う)、ぼくから見て峻ちゃんは、ぼくよりもよっぽど仙人的な生き方をしている人だ。だから、ぼくと峻ちゃんの両方を知る人からしたら、ぼくらは全然違う風に映ると思う。彼は画家で、ぼくはビジネス面でのプロデューサーだ。彼は将来のビジョンなど描かずその瞬間瞬間を生きるタイプで、ぼくは、2030年までに天才研究とアート型ビジネスを完成までもっていくという風に、割と明確な目標をもって日々を過ごしている。それでも、ぼくが峻ちゃんをメインファシリテーターとしてアート合宿を主催しようと思ったのは、根底にある基本的な価値観で共鳴してるからだ。「その人がその人であること。これ以上に大切なことはない」。ぼくもまったく同じような考えでこれまで生きてきたし、『天プロ』というプログラムもそういう価値観のもとで作り上げてきた。
話をペーさんに戻そう。峻ちゃんのそんな風な意図が込められて、参加者ができるだけ日常の思考優位な状態から、自分の感覚や感情が優位な状態に自然な形で移行できるような場が作られていったにも関わらず、初日のぺーさんは戸惑っていた。
広い会場の床全面に敷き詰められた模造紙に、全員が自由に絵を描いていくワークがある。このときには、「絵を描くって思ってたのと全然違って、こんなに自由で楽しいんだ!」と感じて、自分に集中し始めてるメンバーも何人かでてきている中で、ぺーさんは、どうしても「他の人」や「全体」が気になってしまう。
前回のメルマガで書いたが、ぺーさんの中にはこれまで「役立たずになりたくないから、借りを返し続けないといけない」という脳内アプリが入っていた。人の喜ぶ姿や興奮する姿を見るのが好きで、だからこそいつも人の役に立ちたいと思って生きてきた。人が集まる場所では、みんなが楽しい時間を過ごせるようにするために自分ができることは何かを、無意識の習慣として考える。例えば大勢で集まっているときに、一人だけ浮いてて楽しめずにいる人がいたらすぐに気がつくし、例えばその人と一緒に話すことができそうであれば、喜んでそうした。いつも全体を見て、誰かのためにできることを探し(てしまい)、自分がやることを決めていた。
だからこそ、アート合宿でそれぞれが自分に集中するという場は、ぺーさんを余計に混乱させた。全体を見ていろんなことに気づいたとしても、今は自分も含めてみんなが自分に集中する時間なのだ。好きな絵の具を使って、好きなだけスペースを使い、本当になんでも好きなように描いていい。困っている人を助けることや、他の人が楽しめるようにすることは(たとえ他の人だったらやりたがらないことでも)苦なくできるけど、他の人の存在を横において、自分が好きなものややりたいことについて考えてそれをやるっていうのは、ぺーさんの頭の中にはない思考回路だった。まるで大きな川に橋がかかってない状態。向こう岸に渡るには、ゼロから橋をかける必要があった。
(自分が描きたいことってなんだ?)
(今描いてるこんな感じで、合っているのか?)
(ていうか、やっぱり絵を描くってそんなに楽しいことじゃないな)
(この時間は、どういう風に立ち振る舞ってるのが一番いいんだろう)
こんな感じで、ぺーさんの脳内では、次々と「上ぺー」の声が鳴り響く。雑音というレベルを超えて騒音状態だ。一応ワーク中なので手は動かしているものの、心にあらずの状態だ。ぺーさんの場合はまだまだ、「下ペー」が登場する余地はなかった。
・・・
終始戸惑って過ごした初日。夕食が終わった後に、絵を描く会場になっているホールに集まって、何人かで床に座りながらお酒を飲んで話していた(ぺーさんは、酒は飲めない)。自由時間なので、絵を描いている人もいた。
天プロメンバーも、そうじゃないはじめましての人も混ざっていて、いろんな話をしたが、最終的にはぺーさんの話で盛り上がった。ぼくが、ぺーさんが「人生で楽しいって感じたことがない問題」を取り上げたことで、どうやったらぺーさんが楽しいって感じられるようになるのか?っていうことについて、その場にいたそれぞれがぺーさんに質問したり自分なりの意見をぺーさんにぶつけたりしていた。「ぺーさんの悩み」を酒のつまみにして、ぼくを含めた人たちはちょっとずつ議論を交わして、仲良くなっていった。みんなにイジられるという形ではあったが、ぺーさんは「みんなの中心」にいた。
このときの会話の流れでできた造語が、「上ペー」と「下ぺー」だ。「上ペー」とは、思考優位な状態のこと。逆に感覚や感情などの心の声は「下ぺー」っていう呼び方になった。ぺーさん以外の人について話すときでも、「いや、それは”上ぺー”状態になっちゃってるでしょ。もっと”下ペー”を出してあげないと(笑)」みたいな感じで、ぼくたちは飲みのときによくある、その場で生まれたその場にいる人だけがわかる共通言語を使って盛り上がっていた。こうして、ぺーさんは、あれよあれよという間に、「みんなが使う言語」にもなっていた。
このときのことを、ぺーさんは、終了後のアンケートでこう書いている。
自分の悩みに価値はないし、それを人に伝えるのは・困らせる・嫌な思いにさせる・で?って思われる・時間の無駄・相談してもどうせ解決しない、と思ってた。だから40年自分個人の悩みを相談することがなかった。2ヶ月ずっと相談し続けて、そうじゃないことがわかった。アート合宿で参加したたくさんの人に聞いてもらい悩んでいることを知ってもらう中で、それを克服しようとする姿が他の人の背中を押せることを知った。相手が話を聞いて、自分の価値観に気付けることも知った。コントロールはできないけど、相談することを嫌がる人がいるかもしれないけど、自分の悩みを知ってもらうことで、活動を見てもらうことで熱が作れると知った。
この飲み会での時間で起こったことも、ぺーさんにとっては、自分がこうだ思ってきたことを覆す、人生で初めてに近い体験になっていた。人に喜んでもらうことをするならまだしも、自分の悩みそのものや、自分なんかの悩みを相談することが、人の役に立つことがあるなんて、これまで一度も考えたことがなかった。
この時点でちょっとずつ、「上ぺー」によって作られた強固な城は、崩される準備を始めていたのかもしれない。自分が認識してきた世界は、もしかしたら、そうじゃないこともいっぱいあるのかもしれない…。自分が作ってきた世界観が揺らいでいるにも関わらず、飲み会を終えて部屋に帰るぺーさんの身体は、ここ(清泉寮)にやってくる前よりも少し温かくなっている気がした。
そして・・・
・・・
2日目も、朝からいくつかのワークをやり、昼食を挟んで午後になってから、峻ちゃんはまた別のワークをやることにした。最初は、これまでやってきたことと同じだ。自分が描きたいものを十分に時間をとって、自分のキャンバスに描く。この頃には、絵を描くことに慣れてきている人も多く、それぞれの絵には、使われる色においても、使う道具においても、描くものについても、個性が出るようになっていた。まずは、それぞれが自分が描きたい絵を完成させる。
これまでのワークと違うのは、ここからだ。昨日から、4人1組でやるワークがいくつかあり、ワークが終わった後に感じたことをシェアする小グループがあった。今回はその小グループで集まって、自分が描いた絵を右隣の人に渡す。自分のところには左隣の人の絵がやってくる。ここからやるのは、隣の人から渡されたその絵に、自分が好き勝手に絵の具を乗せて、その絵を破壊すること。隣のグループメンバーが描いた絵に、遠慮がちに何かを描く人もいれば、容赦なく自由に全然違うテイストで描き加えるメンバーもいた。ぺーさんは、少し躊躇して、他の3人のメンバーがどんな風にやってるのかを見てみたが、それぞれは目の前にあるキャンバスに集中して、峻ちゃんから与えられた「破壊する」ということを真剣にやっていた。ぺーさんも抵抗をあきらめて、なんとなく思いついた感じで破壊を加えた。このときもまだ「こんな感じでいいのかな」という正解を探すことによって生じる不安があった。
ちょっと間すると、またその絵を右隣の人に渡して破壊を加える。またちょっとしたら次に。という感じで3巡すると、自分の手元に自分の絵が戻ってきた。ぺーさんは、戻ってきた自分の絵を見て内心「おーーー」と思った。「悪くない。むしろ、こっちの方が好きかも」とさえ思った。
ワークはここで終わりではない。峻ちゃんから、今度は、その絵を左隣の人に回すようにというアナウンスがあった。次にやるのは、破壊ではなく尊重。その絵に対するリスペクトの気持ちを持って、その絵が持つ個性が引き立つために何ができるかを感じて、手を加えてみましょうということだった。
ぺーさん自身はまだ気づいてなかったが、このときには「上ペー」は久しくぶりに休憩を取り、「下ペー」がむくっと起き上がってきていた。みんなが等しく、他の人の絵に、尊重ということを大事に手を加える。やるべきことが明確になっているから安心感があった。そして、自分だけでなくランダムにみんなが手を加えるのだ。自分ひとりだとしたらこんな手の加え方でいいのかと不安になってしまいそうだが、みんながそれぞれ手を加えるというワークのルールにも安心感があった。そして、何より、人の絵を尊重の気持ちを持ってというのは、ぺーさんがナチュラルにできることだった。みんなそれぞれすごい絵を描くなぁ、とこのワークに関係なく常々思っていた。だから、そこに自分のリスペクトの気持ちを乗せることは自然とできた。
これもまた3巡して、自分のところに自分の絵が戻ってきた。さっきの破壊のワークの後に戻ってきたときも何か感じるものがあったけど、今回は3人のグループメンバーたちがリスペクトの気持ちを乗っけてくれた自分の絵を見て、その絵から体全体にじわじわじわぁと温かくて軽い液体が広がって、自分の身体の中で空洞だった部分を満たしていくような感覚を覚えた。
この「破壊と尊重」のワークを通して感じたことを、また4人1組のグループでシェアする時間になったときに、ぺーさんはこれまでになく饒舌になっていた。みんなのもとを通って、自分の元に絵が戻ってきたときに感じた、これまでにないなんともいえない感覚を、熱くしゃべった。ぺーさんの中には、みんなから与えてもらったこの感覚をみんなにもわかってほしいという衝動が生まれ、「ぼくの中に生じた感覚はみんなのお陰なんだよ」っていうことを、その喜びを伝えたい気持ちでいっぱいだった。ワークを通して、この4人とつながったという感覚に興奮していた。
ぺーさんは、意気揚々と自分が何をどう感じたのかを話しながら、それを楽しそうにそして嬉しそうに真剣に集中している聞いてくれるメンバーを前にして、「楽しい」とはこういう感覚なのかと思った。
あ!自分は、今「楽しい」って感じてる!
・・・
このときぺーさんに起こっていたことの詳細を終了時のアンケート(※ぺーさんのアンケートは最後に追伸4に乗っけておきます)を見て知ったぼくは、ぺーさんにとっての「楽しい」とは、ぼくにとっての「嬉しい」に近い感情のことなのかもしれないと思った。そしてぺーさんが本当に求めていたのは、自分が熱狂できる何かを見つけることではなかった。少なくとも今この段階では。ぺーさんは、貸し借りや人の役に立てた立てなかったという次元を超えて、人と深くつながることができているという感覚を求めていたのだ。
人とつながれることへの信頼。人とつながることによって得られる安心感と充足感。この感覚こそがぺーさんが、無自覚的に、人生の中でずっと求めてきたことだった。
・・・
ぺーという一人の男が、人生で初めて「楽しい」と感じることができるようになるまでの物語はこれにて完結。
おしまい。おしまい。
・・・
と言いたいところだが、話はここではまだ終わらない。
なぜなら、ぺーさんが、厳密な意味で、「楽しい」を感じられたのは、アート合宿でもこのワークの時間だけだったから。以降の時間は、やっぱりすぐに「上ペー」が「下ぺー」を休ませ、意識の中心にある席に座り直した。
アート合宿は確かに、ぺーさんの人生にとって、他では得がたい経験で、人生が変わるきっかけが生まれた時間だった。ただ、日常生活に戻ってから1週間もすると、やはりいつもの緊張感が次第に戻ってきた。それからのぺーさんの次の課題は、あの「楽しい」という感覚を、どうやったらまた再現できるんだろう?ということだった。
そして、ぺーさんは、またひょんなことがきっかけで、アート合宿で味わったあのなんとも言えないような恍惚感を、今度は自分自身の主体的な取り組みによって、再現しようと挑戦することになる。
第2章ー人生でたった一度だけ、偶然「楽しい」と感じる瞬間に出会うことができた一人の男が、今度は自らの手で二度目の「楽しい」を作り出そうとするための挑戦と成長の物語。
はまた次回以降に。
今日はここまで。
続きはこちらよりどうぞ↓
<全4シリーズ>
【事例】人生で一度も「楽しい」と感じたことがない男の物語
Vol.1「【事例】人生で一度も「楽しい」と感じたことがない男の物語」
Vol.2「クララが立った」
Vol.3「なぜ、人生で初めて「楽しい」という感情が湧いてきたのか?」←本記事
Vol.4「【解説】人の個性を解放するためにぼくがやっているたったひとつこと」

天才研究家やまけん(山田研太)が「アート型ビジネスの考え方と実践方法 」や「最新の天才研究事例」などについて不定期で書いているメルマガです。
他にはない独特な長文芸にある種の中毒性があるとかないとか、噂されるそんなメルマガで、7,000人以上の人が購読してくれています。
特に、アート型ビジネスについては実際のプロデュース事例を含めて、かなり具体的に解説していることも多いです。なので、SNSでの発信よりも、より濃ゆいやまけんの発信を見てみたいという方はぜひ登録してみてくださいね。